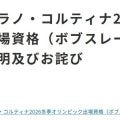【短期連載】令和の投手育成論 第7回第6回はこちら>> 20歳の高卒3年目右腕・佐々木朗希(ロッテ)が4月10日のオリッ…
【短期連載】令和の投手育成論 第7回
第6回はこちら>>
20歳の高卒3年目右腕・佐々木朗希(ロッテ)が4月10日のオリックス戦で完全試合を達成した翌週、17日の日本ハム戦で8回までパーフェクトに抑えながら降板したことで、あらためて投手の「育成論」が議論されている。

2019年夏、岩手大会決勝で登板を回避して物議を醸した佐々木朗希(写真左から2人目)
甲子園を通過点ととらえる球児
周知のとおり、佐々木は大船渡高校3年夏の岩手大会決勝を"回避"した。この決断が物議を醸したのは、勝てば同校にとって35年ぶり甲子園出場だったからだ。
当時は賛否両論だったが、それから3年間で"令和の怪物"は驚異的なスピードとスケールで成長し、「あの時の起用法は正しかった」と國保陽平監督(当時)を讃える声も少なくない。その一方で、高校野球の起用法と今回の偉業を結びつけて語るべきではないという主張もある。
さまざまな意見を見ながらあらためて感じるのは、「甲子園」という存在の大きさだ。100年以上の歴史を誇る日本の文化で、MLB中継でも耳にすることがある。菊池雄星がトロント・ブルージェイズに移籍して初登板となった4月12日の現地放送では、松坂大輔や田中将大という甲子園からメジャーへ羽ばたいた投手たちに加え、花巻東高校時代に菊池と大谷翔平を育てた佐々木洋監督が賞賛されていた。
そうしたなか、日本の現場に目を向けると、甲子園を「通過点」と位置づける高校球児も増えている。
「あいつが面白いのは、『甲子園』という言葉で成長を促してもまったく興味を示さないんです」
京都国際高校の小牧憲継監督がそう話したのは、今秋のドラフト候補として注目される左腕投手・森下瑠大についてだ。「京都でプロのスカウトに一番見てもらえる」ことが同校に入学した志望動機だったという。
京都国際のグラウンドは、右翼60メートル、左翼75メートルほどと決して恵まれた環境ではない。2008年に就任した小牧監督は「個人の能力アップに特化するしかない」と曽根海成(広島)や上野響平(日本ハム)らをプロに送り出し、「京都国際に行けば成長できる」という評判が立った。今や強豪校の誘いを蹴り、入学を望む選手も増えている。
そうして徐々に個々のレベルが高まり、2021年春には同校初の甲子園出場を果たした。同年夏にはベスト4まで勝ち上がっている。
球数制限よりも日程改善の必要性
小牧監督は今も育成を最優先するが、選手たちの成長を加速させた背景には甲子園の存在もある。
「当時(2021年)の3年生が『何がなんでも甲子園に出たい』という学年だったんですよね。それで森下を呼んで、『ピッチャーなんて勝たな評価してくれへんし、勝ったらプロのスカウトの評価も上がるぞ』と言ったんです。そうしたら、『じゃあ、甲子園に連れて行きます』って。それであそこまで上に行ったことで、今度はチームを日本一に導いてドラフト1、2位でプロに行きたいという目標に変わってきたみたいです。
甲子園のあと、秋の近畿大会初戦の試合前、『全球団のスカウトが来ている。履正社に完封でもしたら、ドラフトの順位がひとつ上がるぞ』って言ったら、『完封します』って。あくまでプロありきなんですよね」
京都国際は今春のセンバツを新型コロナウイルスの集団感染で辞退した一方、代わりに出場した近江(滋賀)が滋賀県勢初の決勝まで勝ち上がった。そこで腕を振り続けたのが、こちらもドラフト候補の山田陽翔だ。初戦から4試合連続完投、準決勝翌日の決勝でも先発したが、3回に力尽きた。多賀章仁監督は「彼の将来を見た時に間違いだった」と後悔の念を口にした。
甲子園に出れば、是が非でも勝ちたくなるのはある意味で当然だろう。そのなかで日本高校野球連盟は投手の肩・ヒジを守るために「1週間に500球以内」という球数制限を設けたが、機能しないことは周知の事実になった。現状では監督の判断に任せるという、投手たちの将来を丸投げした格好になっている。
昨年のセンバツを観戦した元中日の吉見一起は先発投手の球数の多さに疑問を持つと同時に、大会スケジュールに改善の必要性を感じた。
「出場順がうしろのチームは球数制限で不利になるじゃないですか。それは間違っていると思います。『球数、球数』と言うなら、みんなが均等になるように。運営の事情はわからないところもありますが、もう少し試合間隔に余裕を持ってもいいのではと思いました」
八田英二前会長が日本高野連のトップだった頃、筆者は「スケジュールを見直せないか」と、聞きにいったことがある。球場と日程の兼ね合いを考えると、休養日を設けるのが精一杯とのことだった。「甲子園で全試合を開催しなくてもいいのでは」という声も巷では上がるが、現場の声を拾うと"聖地"へのこだわりが強いという。
以上を踏まえると、日本高野連としては選手や指導者の要望を聞きながら、年間スケジュールをこなすには現状のフォーマットで可能な工夫をするしかない、という判断になっている。
育成に最適なリーグ戦
対して、もっと根本的な改善を訴える元高校球児がいる。堺ビッグボーイズ中学部の監督で、野球大国・ドミニカ共和国の指導法を日本に伝えている阪長友仁だ。
「『1週間に500球以内』という規定は、球数だけにフォーカスしたから『こんな規定では公立高校は勝ち抜けない』とか、『野球人生の最後に投げたい子はどうしたらいいのか』とかいろんな意見があって、当たり障りないルールになったと思います。でも、低反発バットやトーナメント制など高校野球の全部のあり方を考えて、何が野球界にとって一番いいかを議論しなければいけない」
阪長は新潟明訓高校時代に甲子園の土を踏み、立教大学で主将を務めたあと、青年海外協力隊などで中南米に赴任している間にドミニカの野球を学び、日本球界の育成のあり方に疑問を覚えた。そうしてとくに訴えるようになったのが、トーナメント戦ではなくリーグ戦の実施だ。
実際、堺ビッグボーイズがNPO法人BBフューチャーとして主催する大会は、リーグ戦にあらためている。「負けたら終わり」ではなく「負けても次がある」ことで多くの選手が出場機会を得やすく、投手の登板過多も減り、指導者は送りバントではなく自由に打たせる場面が増えたという。
世界に目を向ければ、野球の基本フォーマットはリーグ戦だ。日本のアマチュア球界で伝統的なトーナメント方式は確かに単純明快で、とくに学童野球では冠大会などスポンサーがつきやすいというメリットもあるが、「負けたら終わり」は育成に合わない。
そこで阪長は全国の高校野球指導者にリーグ戦の導入を訴えてきた。大阪や新潟、長野、群馬などから賛同する高校が現れ、各地で秋に『リーガ・アグレシーバ』として開催されている。
「たとえば10チームが参加して4つが決勝トーナメントに行けるという場合、先発投手のローテーションを組めたり、何勝何敗くらいだったら4位以内に入れるだろうと考えられたりします。だから監督は、ピッチャーの起用をしやすくなると思います」
リーガ・アグレシーバの肝は、球数制限や低反発バットの採用、スポーツマンシップ講習会の実施などを行なうことだ。球数や変化球の制限を含め、指導者たちがルールを決める。そうして高校生が成長できる環境をつくり出そうとしている。
参加校の立命館宇治高校では、公式戦で登板機会のなかった1年生投手が起用され、自信を深めて伸びたという。彼らは立命館大学進学後まで見越して野球をできる環境にあり、リーグ戦のメリットは計り知れないだろう。
問われる甲子園のあり方
反面、予定どおりに実現できなかった地域もある。当初の参加予定校はいずれも甲子園出場を視野に入れる私学だったが、そこに公立が入ってくることになり、全体のレベル低下を懸念して参加をとりやめるチームが相次いだ。
リーグ戦という方式に賛同できても、低反発バットの採用は直接的な強化に結びつくとは考えられない。それも参加を見送った一因だったという。私学の監督、とくに教員免許を持たない者の場合、結果を出せなければクビが飛ぶというシビアな事情もある。
「できない理由はいろいろあると思います」
阪長はそうした現実を踏まえ、新たな提案を口にする。
「現在、大阪の高校野球では180校以上参加して、本気で甲子園を目指しているのはおそらく10校くらいだと思います。ネット上では『リーグ戦なんてできない』という意見もありますが、そもそも甲子園をやるうえでリーグ戦をしようと考えたら『できない』となる。でも、全校が甲子園を目指さなくてもいい。カテゴリー分けをして、『自分たちはここのカテゴリーで、ここを目標にする』としてもいいと思います。
群馬で去年行なわれたリーグ戦では0勝18敗という学校もありました。もちろん勝利を目指しているでしょうが、それだけ負けられるのは逆にすごい。一番学びがあったと思います」
他競技に目を向けるとサッカーでは2003年から「JFAプリンスリーグU−18」が始まり、現在はプレミアリーグとプリンスリーグの2部制となっている。バスケットボールでも昨年、「日清食品リーグ U18バスケットボール競技大会 関東ブロック2021」が始まった。ともに協会が主導し、強化と育成を見据えた環境が整えられている。
かたや、1915年に朝日新聞の販売拡大という目的もあって始まった学生野球の全国大会は、多少の修正はありつつも、過密日程のなかでトーナメント戦が行なわれ続けている。年に2回開催される「甲子園」は日本の文化として根づき、野球界の財産であることに疑いの余地はないものの、令和の価値観に合わない点も多々生じている。
足元に目をやると中学校では部活動のあり方から見つめ直され、球界の頂点に位置するプロ野球でも若手投手の「将来」を見据えた起用も増えてきた。
はたして、甲子園は今後どのような形で存在していくべきか----野球界全体の未来のために、議論が必要な時がきている。
一部敬称略
第8回につづく