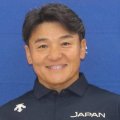時代が昭和だったら、"感動ストーリー"として世の中に発信されていただろう。なにしろ、チームを率いる指揮官の涙が止まらな…
時代が昭和だったら、"感動ストーリー"として世の中に発信されていただろう。なにしろ、チームを率いる指揮官の涙が止まらなかったのだから──。

センバツで5試合、594球を投げた近江エース・山田陽翔
満身創痍でのマウンド
近江のエース・山田陽翔が初戦から孤軍奮闘した。1回戦の長崎日大戦でタイブレークの1イニングを含む延長13回165球。2回戦の聖光学院戦こそ87球で完投したものの、準々決勝の金光大阪戦で9回127球、さらに準決勝の浦和学院戦でも、延長11回170球を投げ抜いた。準々決勝と準決勝の間は中1日。つまり、3日間で20イニング、297球を投げている。
忘れてはいけないのは、山田が故障あがりだということだ。ベスト4に進出した昨夏の甲子園でも雨天ノーゲームを含む6試合に登板し、35イニングで546球を投じた。その疲労から右ヒジを痛め、昨秋の公式戦には登板できなかった。
オフの間の休養と治療で、ようやく投げられるようになったばかりだった。さらに、近江は京都国際がコロナで辞退したことによる代替出場。開幕前日に甲子園出場が決まり、急ピッチで仕上げたのは否めない。
これだけでも体に相当な負担がかかっているのがわかるが、さらにセンバツ準決勝の浦和学院戦の5回裏の打席で左足に死球を受けた。患部をテーピングで固め、足を引きずりながらマウンドへ。満身創痍で声を上げながら投げる姿を見て、多賀章仁監督は試合中から感情を抑えられなかった。試合後のオンライン会見でも涙は止まらず、開始当初は涙声で聞きとりづらいほどだった。
「山田には本当に感動させられることが多くて、甲子園の試合中に涙が止まらなかった。デッドボールが当たってからの1球1球は本当に変わった。魂のこもったマウンドさばきで、本当にすごいと思いました。(試合に勝って)こんな幸せはない。選手には『力が上の相手(浦和学院)に魂が試されるんや。野球は本当にすばらしいスポーツ。今日は勝っても負けても感動発信。そういう試合をやろう』と言ってました」
山田の奮闘に仲間が応え、11回裏に女房役の捕手・大橋大翔が「人生初の柵越え」というサヨナラ3ラン。多賀監督が語った、高校野球らしい誰もが感動するすばらしい試合だったのは間違いない。
だが、問題なのは山田の状態だ。死球を受けた時、多賀監督は「なんで山田が」と思ったという。そして「代えるべきかな......」とも。
「将来がある子ですから、無理をさすわけにはいかない。(マウンドを)降ろせるのは僕しかいない。僕が決断せなアカンのです」
そうは思いながらも、山田を降板させることはできなかった。
「今日は山田で最後までいくと臨んでいた。救いは、初戦に165球投げたあとも『疲労度は夏とは違う。全然大丈夫です』と本人が言ってきてくれたこと。そこにウソはなかったと思います」
ヒジの負担を軽くするため、オフの間、山田はフォーム修正に励んだ。その効果と本人の言葉を理由に、続投を決断した。そして結果的に準決勝には勝った。
自らの意思で降板
だが、その時点で決勝の勝敗は決まっていたと言っていい。なぜなら、最後に戦うのが、準決勝までチーム打率.402、7本塁打の大阪桐蔭だったからだ。山田の体の状態、疲労を考えると、大阪桐蔭に投げさせるのは酷すぎた。
それは、多賀監督もわかっていたはず。指揮官の心中は、オーダーを見ればわかる。これまでは「4番・投手」で出場していた山田を「9番・投手」として起用。この時点で"ファイティングポーズ"すら、まともにとることができなかったわけだ。
事実、決勝のマウンドに立った山田の姿は痛々しいものだった。普段は常時140キロ台(最速148キロ)のストレートは最速135キロで、しかも1球だけ。3回裏、3番の松尾汐恩に打たれた本塁打は123キロ。いつもの山田のイメージから変化球かと思ったが、山田本人は「真っすぐです」と言った。
そしてその直後、自らベンチに合図を出してマウンドを降りた。本来は4番を打つはずの打者が、守備位置に就くことなくベンチに下がったことも、状態の悪さを露呈していた。試合も1対18で近江は大敗を喫した。
「降板した理由は、これ以上、チームに迷惑をかけるわけにはいかないなと。真っすぐが130キロも出ないのがわかっていたので。前の日に170球投げていたし、ボールにうまく力を伝えることができていなかった。2回が終わってベンチに下がった時、星野(世那/2番手投手)に『キャッチボールしてくれ』と伝えました」(山田)
ここでの一番の問題は、監督が交代の指示をしたわけではなく、山田が自らの意思でマウンドを降りたことだ。もし山田が自分で決断しなければ、まだしばらくは投げ続けることになっていただろう。山田の投げるボール、絶対的エースが痛打される様子を見ても、多賀監督は降板指令を出せなかった。山田が自らマウンドを降りたことで、多賀監督も事の重大さに気がついた。
「結果的には、今日の先発は無理だった。回避すべきやったと思います。ここまで来たんで、何とかという気持ちだった。彼の今後、将来を見据えた時に、今日先発するのは間違いだった。大黒柱の責任感で先発を志願してくれたんですが、昨日170球投げての今日でしたから。そこは私が、本人が志願しても判断をすべきだった」
対照的だった浦和学院の起用法
リーダーの最大の仕事は、判断することではない。決断することだ。たとえ意見が1対9でも、1を選ぶ。それができるのは、チームを任されている指揮官しかいない。ましてや、夏にこんなことがあったのだから。
「夏は(2回戦の)大阪桐蔭戦のあと、痛み止めを飲みながら投げていた。それも大会が終わってから知ったんです。『申し訳ない』と本人には謝ったんですけど......」
たとえ無理だと思っても言わない......それが山田の性格である。それは多賀監督もわかっているはずだ。だからこそ、決断すべきだった。だが、多賀監督は山田と交わした約束、本人の気持ちを優先した。
「私は(補欠校ではなく)センバツに選ばれると思っていましたから、『センバツに出たら、5試合おまえでいく』と。それは年明けの最初の練習の日に山田に伝えました」
そのつもりで準備してきた。だから大会中、どれだけ球数がかさんでも、多賀監督は「ウチは山田以外にいない。彼にかけたい」と繰り返した。
だが、理想と現実は違う。たとえ山田本人が「投げたい」と言っても、ほかの選手たちが「最後はエースで」と頼んでも、「ダメだ」と言うのが本当のリーダーではないだろうか。
その意味で、準決勝で対戦した浦和学院の森大監督は対照的だった。準々決勝まで3試合連続で先発していたエースの宮城誇南を近江戦では登板させなかった。試合が延長になっても「宮城に4連投目はさせない。今日は始めから投げさせないと決めていました」と、ぶれなかった。
その結果、試合では敗れたが、もし勝っていたら、決勝でエースを中2日で起用できる。宮城の体を守ることはもちろん、優勝するためにはその選択しかなかったと言える。「明日を考えずに、今日この一戦ということ」と言っていた多賀監督とは正反対の選手起用だった。
絶対的エースのあり方
今大会は、選考会で東海大会準優勝の聖隷クリストファーが選ばれずに話題となった。聖隷クリストファーは東海大会初戦でエースが故障。以降の試合は、控え投手や公式戦初登板の外野手が投げて決勝に進出した。近江も秋は山田が投げられず、投手陣の失点を打撃でカバーして近畿大会ベスト8に入った。エースの不在をチーム全体でカバーして勝ち上がった2校は補欠校。その戦いぶりは選考委員に評価されなかった。
秋は、「エースがいないもの」として選考の対象にされなかった近江は、山田の大車輪の活躍でセンバツ準優勝を果たした。その代わり、エースの酷使という大きな代償を払わされることになった。昨夏の甲子園のあとに投げられなかったように、山田はこの先2カ月は休養せざるをえないだろう。6月頃から投げ始め、夏の大会に間に合わせようとするはずだ。勝ち上がれば、炎天下でまた連投を余儀なくされる。それは、感動でもなんでもない。
絶対的エースがいなければセンバツ大会に選考されない。絶対的エースがいれば連投させる......それはもう令和の時代にそぐわない。高校野球は新たな時代に入るべきだ。あらためてそのことを考えさせられる大会であり、それを象徴した決勝戦だった。