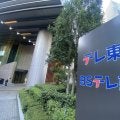連載『なんで私がプロ野球選手に⁉』第7回 攝津正・前編 プロ野球は弱肉強食の世界。幼少期から神童ともてはやされたエリート…
連載『なんで私がプロ野球選手に⁉』
第7回 攝津正・前編
プロ野球は弱肉強食の世界。幼少期から神童ともてはやされたエリートがひしめく厳しい競争社会だが、なかには「なぜ、この選手がプロの世界に入れたのか?」と不思議に思える、異色の経歴を辿った人物がいる。そんな野球人にスポットを当てるシリーズ『なんで、私がプロ野球選手に!?』。第7回に登場するのは、攝津正(元ソフトバンク)。社会人チームに8年間も在籍しながらドラフト指名され、沢村賞まで上り詰めた"雌伏の物語"をお届けする。

JR東日本東北で8年間プレーした攝津正
自分を認めてくれないスカウトへの、恨みがましい思いはなかったのですか?
扇情的な質問にもかかわらず、攝津正は柔和な表情を変えずにこう答えた。
「なんでドラフトにかからないのかな? とは思っていましたね。公式戦はほとんど完璧に抑えて、防御率もずっとよかったので。それでもかからないのだから、何か足りないものがあるのだろうなとずっと考えていました」
いかにも温厚そうな口ぶりと、トゲのない眼差し。実直なサラリーマンと会話しているようで、この人物が沢村賞受賞者だとつい忘れそうになる。
攝津は社会人チームに8年在籍しながらプロ入りし、沢村賞を受賞している。しかも、社会人8年目に台頭したわけではなく、入社4年目にエース格となってから毎年ドラフト候補に挙がる存在だった。そんな投手がプロの世界に足を踏み入れるまで、なぜこれほどの時間がかかったのだろうか。本人や関係者の証言を元に、当時を振り返ってみたい。
三振かフォアボールか
「すごいボールを投げているな」
宮城県の強豪企業チーム・JTの福家大(ふくいえ・だい)は、相手側ブルペンで投球練習する高卒ルーキーに目を見張った。オーソドックスな投球フォームの、右の本格派。いかにも将来有望な雰囲気があった。ところが、試合に入るとその衝撃はトーンダウンした。
「コントロールが悪くて、三振かフォアボールか、という感じだな」
これがJR東日本東北に入社したばかりの攝津の第一印象だった。
秋田経法大付高(現・ノースアジア大明桜高)では甲子園で活躍するなど、攝津は高校時代からそれなりに名前が売れていた。だが、攝津は「もともとコントロールはよくなかった」と振り返る。
「打たれたらムキになって投げていく。勝てるピッチャーではなかったです」
社会人野球は特殊な世界だ。カテゴリーとしてはアマチュア野球だが、その存在意義はプロ球界に人材を送り込むことではない。従業員の士気高揚を存在意義とし、社会人野球最大のイベント・都市対抗野球大会への出場を最大のモチベーションにしている企業チームがほとんどである。
そのためチーム内に大エースがいれば、大事な試合は決まってエースばかりが登板する。好不調の波の激しい投手は、必然的に登板機会が限られる。入社当初の攝津もそんな存在だった。
勝てる投手のヒントはダーツ
転機だったのは入社3年目の夏、投手コーチに阿部圭二が就任したことだった。反復練習を重視する阿部の方針で練習量は3割増しとなり、ブルペンでの投球練習の頻度も大幅に増えた。そんな阿部も攝津の取り組みには舌を巻いた。
「攝津はセンスがあるタイプではなく、努力型の選手でした。毎日ブルペンの同じ場所で投げ込みをして、休んでいる姿を見たことがない。こちらが何も言わなくても、自分で目標を立てて創意工夫ができる選手でした」
目に見えてわかりやすい「創意工夫」は、投球フォームにあった。右腕のバックスイングがみるみるうちに小さくなり、極端にコンパクトなテイクバックになった。攝津の特徴的な投球フォームは、この時期に形づくられている。
ヒントになったのは、趣味としてプレーしていたダーツだと攝津は言う。
「ダーツはマウンドより短い距離なのに、同じ動作を続けて正確に投げるのは難しい。野球でも無駄を省いて再現性を高めれば、誤差が小さくなると気づいたんです」
さらに阿部から「体の一部じゃないボールを扱うには、自分の心もコントロールできないと難しい」と説かれ、常に冷静な精神状態でマウンドに上がるようになった。課題だったコントロールは劇的に改善されたという。
2005年には前年限りで野球部が廃部になったJTから、福家が転籍してきた。攝津は「朝から晩まで走っている」という3歳年上の福家に刺激を受け、より練習量を増やしていく。福家はそんな攝津に対して「泣き言は言わずに黙々と取り組めて、心の強い男だ」と感じていた。
こうして攝津はJR東日本東北の大黒柱となり、実績を積み上げていく。
ミスター社会人になりたい
だが、20代前半と若く、完成度の高い攝津をドラフト指名する球団はなかった。コーチを経て監督になった阿部は、こんな光景を目にしている。
「ドラフトにかかるんじゃないか? といつもインターネットでチェックしていた姿を覚えています。かからなかった時は、声もかけられなくて。後輩たちもドラフトの話はしないようにしていたようです」
勤務地の仙台には、2005年に東北楽天ゴールデンイーグルスが誕生。仙台駅で開催された楽天の春季キャンプ出発式に、攝津はJRの職員として警備に駆り出された。
改札に立っていると、楽天の選手が攝津に話しかけてきた。
「すみません、財布をなくしたんですけど......」
攝津は名前も知らない選手のために、財布探しを手伝った。自分が「そちら側」の世界に行けるイメージは、まったく湧いてこなかった。
「このまま社会人で野球を続けて、32歳くらいで引退するんだろうな。その後は現場に出て勉強して、運転士になるか支社へ行くか。それはそれで楽しそうだなと考えていました」
年々プロ入りへの思いは薄れ、攝津は「ミスター社会人になりたい」という思いを抱くようになる。身近なライバルチームに格好の手本がいた。
「2006年にTDK(秋田県にかほ市)が都市対抗で初優勝していました。エースの野田(正義)さんは来る日も来る日も試合に投げていて、勝てるピッチャーでした。僕も野田さんのようにトーナメントで勝てるピッチャーになりたい。都市対抗で優勝したい。その方向に考えがシフトしていました」
2007年に年齢が25歳になると、もうプロへの思いは消え失せていた。そんなシーズンに、攝津は神がかったパフォーマンスを見せる。
国際大会で4勝の大活躍
11月開催のIBAFワールドカップでは、代表候補に入っていなかったにもかかわらず、練習試合の相手として登板した内容が評価され代表メンバーに選出。田澤純一(当時・新日本石油ENEOS)らと臨んだ本戦では、攝津は4勝を挙げる大活躍で大会優秀投手(右投手部門)を受賞する。
「相手が誰かわからないので、フラットな状態で投げられたのがよかったのかもしれません」
攝津はそう振り返る。ワールドカップが閉幕した翌日、ドラフト会議が開かれた。
だが、社会人7年目の攝津の名前が呼ばれることはなかった。それどころか、皮肉なことにチーム内の後輩である平野将光が西武からドラフト1位指名を受けた。
チームメイトの福家は複雑な心境だったという。
「攝津は球速が140キロ台前半で、コントロールがまとまっていてゲームをつくれました。でも、社会人のエースとしてはいいけど、プロのスカウトには面白みがないのかなと思っていました。平野は粗削りなんですけど、上背があって球速は攝津より速い。プロのスカウトが面白いと感じるのは平野のようなタイプなんでしょうね」
すでにプロへの思いを断ち切っていた攝津は、素直に1歳年下の後輩を祝福した。
「平野とは仲がよかったですし、自分の指名がなかったからといって何とも思わなかったです。平野のボールはピュッと伸びて140キロ後半が出たし、足も速くて。こういうヤツがプロに行くんだろうなと思っていましたから」
悲壮感はない。結果を出したからといって、認められる世界ではないと攝津は割り切っていた。
そんな「ミスター社会人」を目指して前を向く攝津を、ずっと見守り続けるスカウトがいた。
(後編につづく)