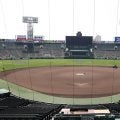昭和の名選手が語る、闘将江藤慎一(第2回)第1回を読む>>1960年代から70年代にかけて、野球界をにぎわせた江藤慎一と…
昭和の名選手が語る、
"闘将"江藤慎一(第2回)
第1回を読む>>
1960年代から70年代にかけて、野球界をにぎわせた江藤慎一という野球選手がいた(2008年没)。ファイトあふれるプレーで"闘将"と呼ばれ、日本プロ野球史上初のセ・パ両リーグで首位打者を獲得。ベストナインに6回選出されるなど、ONにも劣らない実力がありながら、その野球人生は波乱に満ちたものだった。一体、江藤慎一とは何者だったのか──。ジャーナリストであり、ノンフィクションライターでもある木村元彦が、数々の名選手の証言をもとに、不世出のプロ野球選手、江藤慎一の人生に迫る。

ダンベルでトレーニングをする江藤慎一
少年時代の江藤慎一は後の豪傑イメージとは程遠かった。気管支が弱いうえに難病のジフテリアにかかり、長く運動を禁止されていたのである。尚武の気風を尊ぶ九州は熊本の地で体育の時間に参加することが許されず、教室からの見学を余儀なくされることは、実につらかったと自著(『闘将火と燃えて』)に記している。
4人兄弟の長男である江藤は、その実家のことを、子だくさんで明るく、しかし、貧しい家庭であったことを「まるで映画の『つづり方兄弟』のようであった」と書き残している。『つづり方兄弟』(1958年製作)は、極貧のなか、得意な作文を支えにたくましく暮らす大阪交野市の野上三兄弟を描いた物語であるが、劇中で8歳の次男・房雄がまともな医者にかかることができず、劇薬を飲まされて腸マヒを起こして急逝するという貧困ゆえの痛ましさが、ひとつのテーマになっている。江藤家もそれに比すというであれば、いかに赤貧洗うが如しの状況であったか、推して知ることができる。
しかし、モヤシの様だった少年がたくましくなっていくのは、その厳しかった家計を助けるために新聞配達を始めてからであった。小学生が重い朝刊の束を抱えてまだ暗い早朝から150軒の家庭を回るのは、苦行でもあったが、足腰の鍛錬につながって、体力がつき、学力もそれに比例して伸びていった。
野球との出会いは父親がかつて八幡製鉄の外野手であったことから、自然と手ほどきを受けていった。ポジションは捕手を自らが選んだ。これには理由があった。当時暮らしていた山鹿市内の社会人の対抗試合で父のチームと対戦していた相手の村上行雄という捕手が、タイムリーヒットによる本塁突入をブロックして失点を防ぎ、そのまま送球してランナーも刺してダブルプレーを完成させた。ところが、併殺直後この村上捕手は崩れ落ち、血を吐いてそのまま亡くなったのである。まさに命がけの本塁死守であった。
これを観戦していた小学生の江藤は「父ちゃん、野球やるならわしは一番、きついところがよか」と捕手を志願したのである。「いかん、キャッチャーだけはいかん。大ケガをする」死亡事故を眼前で見て当然、親は反対したが、(この時に送球で刺されたランナーが父の哲美であった)「いやや、皆が嫌でも誰かがキャッチャーをやらんならんなら、わしがやると」と引かなかった。
以降、江藤はプロに入団するまで捕手一筋になるのだが、その選択の理由が、誰もが嫌がるきついポジションなら自分がやるというものであった。コリジョンルールなど影も形もない時代に、チームのために身体を張ろうとする豪放な性格はここから、垣間見られるが、その一方で捕手をやることを決意して以来、日課としてつけていた野球ノートには学究メモかと思われるほどに几帳面な文字が毎日埋められた。
捕球の仕方、サインの出し方、キャッチャーフライの取り方等々、図解入りで記されたそれは緻密で繊細な江藤のもうひとつの性格を物語っている。このノートは中学、高校、社会人と続けられ、積み上げればそれぞれが30センチの高さに及んだ。興味深いのは、捕手としての技術についてページを費やしながら、必ず最後は「捕手は、その上、自分のチームに元気をふきこむものでなくてはならない。絶えず激励の言葉を送る様につとめなければならぬ」というようにリーダーとして全体を鼓舞することを自らに課して締めている。
高校は熊本商業に進んだ。名門熊本工業に阻まれて甲子園には出場を果たせなかったが、江藤の存在は中央大学球界にも知られており、早稲田からの誘いがあった。神宮でのプレーに魅力を感じていた。しかし、家庭の事情がそれを許さなかった。夜半、素振りをして寝床に戻ると、3人の弟が川の字になっていた。その寝顔を見て進学を断念した。3人を高校、大学に進学させることを考えれば、すぐにでも一家を支える必要があった。阪神タイガースが、同期である熊本工業の西園寺昭夫と一緒に入団の声をかけてきたが、まだ高卒で行くには自信がなかった。
最終目標をプロに置きつつも江藤は当時の九州社会人野球の雄、日鉄二瀬に就職することを望んだ。すでに6人の採用枠は埋まっていたが、半ば押しかけるような形で野球部のテストを受けて入社を懇願すると、臨時工での採用が許された。当時の日鉄二瀬の日給は276円で、1か月働いて野球手当を入れても7000円にもならないが(当時のサラリーマンの平均月給は16608円)、その内の5000円を実家に仕送りし続けた。張本勲が「省三(江藤家の三男、後に巨人、中日ドラゴンズでプレー、慶応大学で監督)は慎ちゃんに頭が上がらんだろうな」と言っていたのは、江藤が当時から弟の学費などの面倒をみていたからである。
江藤が日鉄二瀬への入社を志望したのは、ただ強いチームというだけではなく、プロに行くための指導を仰ぎたい人物が監督をしていたというのが、最も大きな理由であった。指揮官の名は濃人渉(のうにん・わたる)。後に、中日、ロッテで監督を歴任し、新人エース権藤博を連投させ続けたことで、「権藤、権藤、雨、権藤」の惹句を生んだ人物でもある。
昭和31年、濃人は合宿所に入ったばかりの江藤に「お前は何を目的に二瀬にきたんじゃ」と問うてきた。「はい、自分はプロに行くために監督にしっかりと仕込んでもらいたくて参りました」。濃人はこれを聞くと「わかった。3年やってプロに行けんかったら、いさぎよう諦めるんじゃ」とだけ答えた。
この頃の二瀬のメンバーは寺田陽介(南海ホークス)、橋本基(毎日オリオンズ)、黒木基康(大洋ホエールズ)、吉田勝豊(東映フライヤーズ)、古葉竹識(広島カープ)、井洋雄(広島カープ)ら、後にプロに羽ばたいていく選手が研鑽を競い合っており、「濃人学校」と呼ばれていた。
日鉄二瀬炭鉱は、福岡県飯塚市の北西部に位置しており、真裏には西町という炭鉱夫相手の遊郭があった。まだ売春防止法が施行される前であり、夜ともなれば、絶え間ない嬌声と客引きの声が、周辺にこだましていた。二瀬野球部のグラウンドと合宿所は、よりによってこの西町に近接していた。それでもこのチームから、プロへ進む多くの選手が生まれたのは、かように誘惑の多い環境下でも酒色に溺れる余裕すらなくなるほどに濃人による徹底的な猛練習が課されたためと言われている。「濃人学校」の生徒たちは、指導法、戦術、哲学においてこの監督から極めて大きな影響を受けていた。
当時の濃人を語れる貴重な野球人が、江藤の1学年上で、同じ熊本の済々黌高校から前年に二瀬に入社していた古葉竹識である。昭和50年のシーズン途中に広島カープの監督に就任し、初の優勝に導き、以降も黄金時代に導いた名将は、選手育成のうえでその模範とした監督は、ノンプロ時代に薫陶を受けた濃人渉であったと公言して憚らなかった。2021年11月12日に逝去した古葉は生前に行なったインタビューでこんな言葉を残している。
──古葉監督にとって濃人監督の影響というのはかなり大きなものがあったのでしょうか。
「僕にはもうそれが一番にありましたね。(昭和)50年にカープで突然ジョー・ルーツ監督が辞任されて、私が後釜にすえられた時、真っ先に濃人さんに相談しました。『私はやっていけるでしょうか。プロの監督として最も大切なことは何でしょうか?』と伺ったのです」
濃人は広島で生まれ育ち、広陵中学でセンバツ甲子園に出場している。原爆が投下されたときは30才で爆心地に近い市内・皆実町で被ばくしており、教え子の古葉との関係だけではなく、復興のシンボルとして産声をあげた市民球団のカープとは親和性が強かった。ルーツが築いた礎の上に何を足すべきか、強化予算の少ないチームにおいては初優勝に向けて何が必要なのか、教えを請うた。
「カープを率いるうえで重要なのは『それは選手をしっかり見ることだ』と言われました。『監督として大事なことは、練習から試合まで選手の振舞いや所作を見落とさないことだ。見るというのは、表に出る能力や好不調の波、それだけではない。選手の気持ちのなかまで見てやることだ。何を考えているのか、内心こそ見落とすな』と。確かに必ず練習がスタートするアップの時から、ずっと選手を見ておられました」そして、そのために古葉のトレードマークともなったベンチ内での立ち位置も実は濃人の影響であったことを吐露した。
「僕がいつもバットケースの横に立って戦況を見ていたのは、濃人さんのスタイルでした。あの場所がグラウンドのすべてを把握できるからです。ピッチャーの投げるボールも球種やコース、内野のシフト、ランナーの動き、全部わかるんです。ここで、スライダー、はい、フォークボール、それを打たれた時にうちの野手はきちっとしたスタートができているのか。見極めて起用しないといけない。試合が始まれば、フィールドの選手が打球を止めれられなかった、捕れなかったというのは誰の責任でもないんです。それはもう使った監督の責任です。
今、プロ野球は各チーム支配下選手が70人の契約で、育成契約の選手も含めて2軍、3軍がありますよね。しかし、僕が監督の時は60人しか契約できない時代でした。カープにおいては、この60人の戦力のなかで、戦う相手5球団との比較をして、誰を使うのか、ここはもう少し補強しないといけない、このポジションの選手を育てないといかんというような分析を行なうわけです。実は濃人さんとは、ここにいい選手がおるぞ、あの穴が埋まるぞ、見に行こうと言われて一緒に見に行くことが結構あってそこで選手の見方を学ばせていただきました」
試合の采配のみならず、濃人ゆずりのチーム編成の妙こそ古葉の真骨頂であった。まだ20代だった山本浩二、衣笠祥雄、外木場義郎、池谷公二郎、三村敏之......、古葉が濃人から伝授された選手の気持ちのなかまで観察したうえでの起用は当たり、それまで3年連続最下位だったカープのV1は達成された。その後、60人登録での戦力状態を見据え、この年に投手で入団した高橋慶彦をスイッチに転向させ、ポジションの補強として急務だったショートとして育てあげていく。
高橋以降もポリバレントな選手の育成にぬかりなく、カープは正田耕三、山崎隆造とスイッチヒッターの系譜が続く。濃人は二瀬で預かった選手をプロとして使い勝手のよい選手として送り出したが、古葉はそれに準じるように入団後も自らの手で起用しやすい駒に染めていった。濃人は監督としてつらいことがあると富士山を見に行って心を落ち着けたが、このメンタルケアのやり方もまた古葉はそのまま踏襲している。
古葉の監督としての原点は濃人であったが、そもそも古葉のプロ入りも濃人が大きく関与している。濟々黌高から、専修大学に進んだ1年目の夏休み、熊本に帰省して母校の練習を手伝っていた古葉のプレーを見た濃人が「もしもプロに行きたいのなら、二瀬に来い。自分がその希望をかなえてやる」と誘ったのである。
古葉は都市対抗で活躍していた九州の名伯楽にすでに心酔していた。「濃人監督に鍛えていただいたら、自分でも絶対にプロにいけるという気持ちがあったんです。だから、僕は大学をすぐ辞めてしまいました。濃人さんのチームにとっていただけたのなら、必ずプロの選手になれると信じていたのです」
インタビュー中も終始古葉は、亡き濃人に対するきれいな敬語を崩さなかった。事実、二瀬で名ショートとして名を上げた古葉は2年後にカープ入団が決まる。
そして古葉の1年下で同様にプロ入りに向けて鍛えられたのが、江藤であった。古葉は江藤をどう見ていたのか。
「済々黌高校時代から、1学年下の江藤君のことは知っていました。やっぱりバッティングが他の選手と違っていました。型をしっかり持って、上だけでなく下半身、足を使ってラクに腕が振れるようにというのが大事ですが、それができていました。弟さんたちを大学に行かせるために自分はプロに行くんだというようなことを言っていました」
かく言う古葉もまた弟の学費を払うためにプロを志したという経緯がある。昭和30年代は家族を養うためのプロ野球だった。
「私や江藤をプロに行かせるために濃人さんの練習は確かに厳しかったです。お前たち、全体の練習が終わったらノックをするぞ、100本だ、俺が打ってからスタートせえ、と言われて始まるんですね。こちらは100という目標に向けてボールに飛びついていく。それで終わると思って力を出しきるんですが、そこから400本続いて結局、500本になるんです。
そこまでくると、小手先ではなくて全身の力がいる。ヘトヘトになるんですが、つまりはプロとして試合に出続ける体力をつけろということだったんですね。社会人と違ってシーズン中はほぼ毎日ゲームがある。プロは試合に出てなんぼの世界です。せっかくレギュラーになれる技術があってもすぐにバテていては使われなくなる。あの世界に飛び込む以上は、1年目から使われ続けるようになって行けということでした」
濃人が好んだ練習に "無休止符"というものがあった。これはアップに始まり、現在では見られなくなったウサギ跳び、6キロランニング、素振り、ノックと続くのだが、この間、ボタ山から炭塵が舞い降りるグラウンドでは、一切のインターバルがなく続けられる。練習が終われば満足に歩くこともできないというメニューが組まれ、完全燃焼した選手たちは目と鼻の先の新町遊郭に遊びに行くどころではなかった。
一度、合宿所に引き上げてきた新人選手が階段を二段ずつ軽快に上がるのを見た濃人は、「まだそんな元気があるのか!」と集合をかけて、動けなくなるまで追加練習を施したことがあった。とにかく全力を出しきって1日を終えろ、余力を残すなという教えであった。
社会人からプロに入った以上は、結果が出なければ解雇はすぐそこにある。初年度は身体作りという悠長なことは言わず、1年目から勝負という濃人の信念は後の権藤の起用を見てもわかる。
有酸素運動を常に取り入れたハードな練習のなか、江藤は、二瀬入団1年目は正捕手である瀬崎昌引の牙城を崩せず、ブルペン捕手のまま、シーズンを終えた。肩も負傷し、失意のなか、同僚の福沢幸雄(後に中日)と相談して一時は野球を辞めて自衛隊に入隊しようという決意さえ固めていた。
しかし、結局濃人にはきり出せず、2年目を迎える。自信をなくしかけていたが、昭和32年5月、都市対抗予選に向けて行なわれた大阪への強化遠征試合で、ポテンシャルの高かった打棒が爆発した。泉鉄八尾、住友金属、オール鐘紡との3試合で10打数6安打。打率6割でレギュラーの座をつかむとその勢いのまま、都市対抗地区予選でも広いことで知られる大谷球場で2本のホームランを放った。本大会では、鐘化カネカロン戦で捕手としてエース村上峻介の大会史上初となる完全試合をリードし、打っては唯一の得点となるソロアーチをかけた。
この活躍によってプロから大きな注目を浴びることとなったが、それ以前より江藤の潜在能力を見抜いていたスカウトがいた。中日ドラゴンズの柴田崎雄である。福岡県嘉穂郡碓井の在であった柴田はかつて戦時中に存在したプロ球団、西鉄軍での先輩であった濃人の指導するグラウンドをふらりと訪ねたことがあった。その時二瀬の練習を見ていた炭鉱夫たちのこんな会話を耳にした。
「あのキャッチャーは、すごう腕っぷしが強そうじゃ」「濃人さんは、どこからかよか選手ば探してきよっと、そして具合ように育てるのがうまいけん、きっとあのキャッチャーも大物になるばい」
粗削りだが、当たれば格段の飛距離を出す。いつも大声を出して味方を鼓舞する元気のよさも頼もしい。大器の片りんがそこかしこに見える。それが19歳の江藤の第一印象だった。
中日球団代表の平岩治郎の命で正式にスカウトに就任した柴田は当時「打てない中日」と言われていた貧打のチームの戦力補強を依頼された。その時に真っ先に思い浮かんだのが江藤だった。柴田の著作、『いい人たちばかりの中で』からその内心を引用する。
「今も昔も変わりはないが、当時の中日は選手を採用する基準を特に『打てる』という点にしぼっていた。──中略──あいつならきっとやってくれる。第一、ゼントルマン揃いだとか、お嬢さんのような上品なチームだとか皮肉をこめて批判される、よく言えばいぶし銀のような地味な、悪く言えば無気力なくすんだチームカラーに、強烈なかってない原色を加えることにもなる。体質改善の原動力として活躍するに違いないあの逞ましい、元気を絵に描いたような江藤慎一をとってやろう」
プロ球団の選手獲得において「高卒社会人は3年間の在籍後にドラフト指名」という規約のない自由競争の時代である。2年目にあたる昭和32年の秋に柴田は濃人のもとを訪ねた。急成長を遂げた江藤のバッティングを見やりながら、「あの江藤はどうですか」と早々に切り込んだ。
「ほう、君もあれに目をつけたか」濃人は、他にも西鉄(ライオンズ)と広島から話がきていると言った。「本人の希望にそってやろうと思うが、今年はまだ駄目だ。この先の1年があいつにとって最も大切なんだ。もう1年待ってくれたら、わしがもっとプロ向きのすごい選手に育て上げるから」
濃人は、すでに江藤にも今年はまだ辛抱せよ、あと1年鍛えてからプロに行けと通達していた。代わりに俊敏な動きを見せるショートストップを指さした。「それより、あの古葉はどうだ? あれは仕込んであるのですぐに戦力になる」
古葉はもう完成しており、翌年カープに入団して1年目からレギュラーになっていくのだが、柴田はこの時に古葉を獲らなかったことを再三悔やんでいる。
高校や大学を中退させてプロに入団させるという剛腕スカウトもいた時代であるが、中途半端な育成の状態でプロには出したくはない、という濃人の意向を尊重した柴田は、1年待つことを約束した。
それでも家庭環境だけは確認しておこうと、江藤の実家のある下益城郡松橋へ向かった。探しあてた長屋の家は、戸の立てつけが悪く、障子は破れ、畳もささくれ立ったままであった。初対面にも関わらず、父の哲美は迎え入れてくれたが、貧しい暮らしは出された茶の湯飲みからも感じ取れた。
しかし、柴田は鴨居に飾られた大量の賞状を見て驚嘆する。そのほとんどが、野球ではなく、慎一の学業の表彰や各学年で級長に任命された辞令の数々であった。あの豪快な炭鉱のチームで大声を張り上げている捕手が成績優秀な秀才であったことに柴田は驚きを禁じ得なかった。
父の哲美は「慎一は息子とは言え、もう一切を濃人さんに任せていますので、監督さんがあと1年待てと言われたならば、申し訳ないですが、そうしてもらえませんか」と繰り返した。
柴田も異論なく、顔つなぎ以上の期待をしていなかったが、ふと飾られた一葉の写真に目がいった。哲美が八幡製鉄時代に鉄鉱石収集のために乗船した日本郵船の有馬山丸であった。「お父さん、こりゃあ、有馬山丸じゃなかとですか!」柴田の驚きに哲美も反応した。「えっ、あんたもその船を知っとるとですか?」
柴田は戦時中在籍していた巨人軍から、入隊志願をしてシンガポールへ運ばれる際、門司港から乗せられた船がこの有馬山丸であった。「それは奇遇ですな」戦前に同じ輸送船に乗っていたことがわかると一種の同族意識が芽生えて、これで哲美と柴田の距離が一気に縮まった。
スカウトの立場からすれば、西鉄や広島も動いているとなると、1年待つにしても特別なアプローチを考えなくてはならない。何となれば、熊本育ちの江藤自身は、九州をフランチャイズにする西鉄の子どもの頃からのファンであったという。加えて、この年のライオンズは魔術師と言われた三原脩を監督に据え、鉄腕・稲尾和久、流線型打線の豊田泰光、中西太、大下弘らの活躍で2年連続日本一を達成していた。
対して中日は初優勝から時間も経ち、かろうじてAクラスにいる状態だった。チーム防御率はリーグ1を誇ったが、打撃成績は.219で5位、本塁打数は最下位だった。柴田にすれば、縁もゆかりもない名古屋のチームの名刺を出して誘っても「あんなボケちょるチームは、好かんばい」と言われてしまえば、それまでであった。
しかし、ここで築いた哲美とのパイプは大きかった。その後も柴田は折を見ては名古屋から松橋に通い続けた。飯塚市内の二瀬の選手ご用達のとんかつ屋にも根回しをして球団のツケでステーキやハンバーグが食べられるようにして栄養をつけさせることにも余念がなかった。
予想どおり、3年目を迎えて江藤はさらに成長を重ねた。明確にプロ入りという目標に向かって、倍近い練習量を自らに課したことで、打撃にさらに磨きがかかった。シーズンが開幕すると、不動の4番捕手として日鉄二瀬を都市対抗準優勝、産業別大会での優勝に導いた。プロからの勧誘は殺到したが、早い段階から、柴田が密着し、リードしていた中日が契約を交わすことになった。
他球団からの巻き返しはすさまじかった。阪神時代に立命館大学を中退させて吉田義男を入団させ、その吉田と三遊間を組み「長嶋よりもうまいサード」と言われた三宅秀史を大洋との争奪戦の末に獲得して「まむし」の異名をとった大毎オリオンズの青木一三スカウトは金額を空けた契約書を哲美に差し出し、「ご子息の慎一君の評価はこれです。お好きな数字を書いて下さい」と迫ったという。
しかし、哲美は義理堅く、最も早くから声をかけ、1年待ってくれた中日を選んだ。契約金500万円、年俸120万円は、他球団よりも額は少なかったが、江藤本人も異存はなかった。背番号は8。
夏の甲子園で準優勝投手となった徳島商業の板東英二、多治見工業のエース河村保彦らが同期であった。くしくもこの3人は柴田が担当していた。
(つづく)