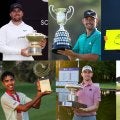連載「高校サッカー異端児たちの3年」第1回、躍進した相生学院が兵庫県大会で準優勝 発足からわずか3年で、全国高校サッカー…
連載「高校サッカー異端児たちの3年」第1回、躍進した相生学院が兵庫県大会で準優勝
発足からわずか3年で、全国高校サッカー選手権の舞台にあと一歩と迫ったチームがある。淡路島を拠点に活動する兵庫県の相生学院高校サッカー部は、県大会決勝で滝川第二高校に0-1で敗れたものの、強豪相手に互角の攻防を演じた。彼らはいかにして、その場所へと駆け上がったのか。通信制高校として、育成年代の新たな可能性を示した総監督の上船利徳と選手たちの3年間を振り返る。(取材・文=加部 究)
◇ ◇ ◇
上船利徳が「エリート人材育成淡路島学習センター」を起ち上げたのは3年前のことで、本サイトでも「プロを目指す選手たちやエリートになれる人材の育成」を掲げる当時25歳の校長の抱負やビジョンなどを紹介した。そして一期生が最上級生になり、早くも成果は表れた。
上船が総監督としてチームを率いた相生学院は、全国高校サッカー選手権兵庫県予選で決勝まで進み、岡崎慎司、加地亮ら日本代表選手たちを輩出してきた伝統校の滝川第二を最後まで苦しめた。しかも一期生の福井悠人は在学中にカマタマーレ讃岐の一員としてJリーグにデビュー。複数のJクラブで練習参加を経験してきた日高光揮ら3人の選手たちも、ドイツへ渡り引き続き夢を追う予定だ。
確かに淡路島には、2002年日韓ワールドカップでイングランド代表などが使用した天然芝のピッチや人工芝の室内練習場、フットサルコートなどがあり、随時それらの施設を利用できる恵まれた環境があった。また通信制の利点を活かし、午前中からトレーニングに励み、空き時間を個々の裁量で効率的に使うことも可能だった。しかし、いくら好条件を揃えても、新設したばかりの通信制高校が、いきなり有望な中学生を集めるのは難しい。一期生の中には、全国大会のピッチに立ったことのある選手が1人もいなかった。実際に発足当初は、近隣の街クラブで1学年下のジュニアユースのチームに敗れていた。
もちろん上船は、プロを目指す志の高い選手たちを募った。だが中学年代でも国内のトップレベルを体感したことのない選手たちに、言葉だけではプロの厳しさは伝わらない。
上船には明治大学サッカー部での指導経験がある。例えば2020年の同校サッカー部卒業生は、15人中12人がJリーガーになった。大半がプロになる環境だったので、そこに辿り着くための基準は把握していた。だから淡路島のトレーニングの中でも、コントロール、パスのスピードや質、受ける前の予備動作やデュエルも含めて、自分の知るプロの基準を求め続けた。ただし反面、彼らに理解してもらうには、体感してもらうしかないとも考えていた。そこで敢えて大学生や社会人チームなど格上の相手との練習試合を、積極的に組み込んでいった。
「初年度は先輩がいなくて文化もない。でも『初年度だから仕方がない。どこの学校も最初は弱かった』と言い訳はしたくなかった。僕を信じて淡路島へ来てくれた選手たちを、未来の土台にはしたくなかったんです」
一期生の3年生12人「本当に続けてきて良かった」
上船がプロの基準を求めたのは、ピッチ上だけではなかった。
「トレーニング以外の時間の使い方、人間力、自主練習の姿勢……、日常生活も含めたすべてでプロの基準を要求してきました。プロの選手たちには当たり前のことなので、それができなければ目標は達成できない。もちろん、中学生時代までの経験とのギャップが大きく、それを苦しいと感じた選手たちが多かったのも事実です」
結局プロジェクトがスタートして初めての夏には、プロを目指して入学してきた21人中16人が「一度気持ちを整理したい」と自宅へ帰り、10人はそのまま退学した。「大学生との試合が多く自信をなくした」という声もあれば、「食事や掃除当番を守らないヤツがいて、サッカーに集中できない」ことを理由にする者もいた。残る側にもやめていく側にも甘さがあり、本当にプロを目指すのがどういうことなのかを描けている選手は少なかった。
しかし淡路島で過ごしてきた編入生も含めた12人の3年生は、今「本当に続けてきて良かった」と話している。前途多難な船出で波乱万丈の航海を経たメンバーは、必ずしも全員がハッピーエンドを迎えたわけではない。だが最後の選手権予選に挑む12人は、レギュラー、サブ、メンバー外と立場は分かれながらも全員が一枚岩になり、紛れもなくそれぞれの役割を全うした。
例えば内田楓は、唯一3年生で決勝戦をスタンドから見守った。本来なら途中からアルゼンチンへの留学を考えていたが、コロナ禍で叶わなかった。それでも土壇場までモチベーションを落とさずに、メンバー入りを目指した。
「決勝戦前日のトレーニングでも誰よりも頑張った。後輩たちにも、そんな姿勢は伝わったはずです。当日も保護者の方々にユニフォームを配り、チームが良い雰囲気で戦えるように全力で支えてくれた。負けた瞬間には一番悔しそうに涙を流していました。僕は常々『求められることをこなすのは当たり前。何事にも想像以上のことをやってのけるのが超一流』だと話してきました。楓はピッチ外でも超一流の仕事をして盛り上げてくれた。本当に感動しました」(上船)
相生学院はプロを目指すプロジェクトなので、すでに讃岐に合流していた福井は選手権に出場しなくても良かったし、スタッフもそのつもりでいた。だが選手権出場は、福井がどうしても譲らずに切望した。
個々が人間的にも成長しチームとして結束
「僕が讃岐でJ3にデビューした時に、チームメイトのみんなが一生懸命応援してくれたんです。今度は僕がアイツらを全国へ連れて行ってあげたい」
実際、福井は選手権予選を通して別格の創造性を見せた。数的不利でスペースが限定された状況でも、瞬時にトップスピードに乗り、それでいてコントロールにブレがなかった。
改めて上船が振り返る。
「彼はプロの力がついたので讃岐に合流させ、想像以上の成長を見せました。それまでも良い選手でしたが、高校レベルでも毎試合起点になっていたわけではなかった。適切なタイミングで効果的な刺激を与えられたからだと思います」
チームで勝つことより個の育成に主眼を置いたプロジェクトだった。だが3年間を経て、個々が人間的にも著しい成長を遂げた集団は、仲間を思いやる一つのチームとして結束していた。(文中敬称略)(加部 究 / Kiwamu Kabe)
加部 究
1958年生まれ。大学卒業後、スポーツ新聞社に勤めるが86年メキシコW杯を観戦するために3年で退社。その後フリーランスのスポーツライターに転身し、W杯は7回現地取材した。育成年代にも造詣が深く、多くの指導者と親交が深い。指導者、選手ら約150人にロングインタビューを実施。長男は元Jリーガーの加部未蘭。最近東京五輪からプラチナ世代まで約半世紀の歴史群像劇49編を収めた『日本サッカー戦記~青銅の時代から新世紀へ』(カンゼン)を上梓。『サッカー通訳戦記』『それでも「美談」になる高校サッカーの非常識』(ともにカンゼン)、『大和魂のモダンサッカー』『サッカー移民』(ともに双葉社)、『祝祭』(小学館文庫)など著書多数。