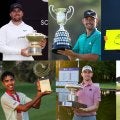今季、1996年以来となるリーグ制覇を果たしたオリックス。中嶋聡監督のもと、エース・山本由伸、強打者・吉田正尚といった…
今季、1996年以来となるリーグ制覇を果たしたオリックス。中嶋聡監督のもと、エース・山本由伸、強打者・吉田正尚といった投打の軸を筆頭に、新戦力が次々と台頭するなど、これまでの鬱憤を晴らすかのような圧巻の戦いを見せた。そんな2021年のオリックスは25年前の"V戦士"の目にはどのように映ったのか。今回、藤井康雄氏、大島公一氏の2人に1996年の「仰木野球」と2021年の「中嶋野球」について聞いた。

オリックスを25年ぶりのリーグ制覇に導いた中嶋聡監督
■藤井康雄氏
── 25年ぶりのリーグ優勝。当時と今を比較して、チームにはどんな共通点、あるいは違いがあるでしょう。
「優勝するだけあって、当時も今もチームバランスがいいですね。今なら山本由伸、宮城大弥などの先発陣が盤石で、攻撃陣では吉田正尚という傑出した打者を軸に、宗佑磨、杉本裕太郎、紅林弘太郎ら一軍としては新戦力が台頭して得点力をアップさせた。
当時は長谷川滋利、星野伸之、野田浩司ら先発陣がいて、鈴木平、野村貴仁、平井正史らの中継ぎ抑えに繋いでいく。打線はいうまでもなく"猫の目打線"です(笑)」
── 前日と翌日と、まるで猫の目のようにクルクル変わる打線からついた異名ですね。
「そうです。当時の仰木彬監督が就任した94年から打者の起用は相手投手との相性重視になっていたのですが、日本一になった96年のみならず、初優勝した前年の95年にはすでにクルクル変わっていたんです。前日に猛打賞の活躍をしても、翌日は先発との相性が悪ければスタメンを外れる。そんなことは日常茶飯事でした。不動だったのはイチローと田口くらいだったかな」
── 選手としては面白くなかったのでは?
「そりゃ面白くはなかったですよ。ただ起用に文句を言うわけにもいかない。データは正直ですしね。実際、打てていないから外されたり、打順を下げられたりするわけで。逆に不調でも、相手投手から打っているという理由で4番に戻ったこともありました。僕の場合、当時ダイエーだった工藤公康投手はお得意様だったので、前日に6番で無安打でも、翌日の試合は4番に上がっていたり(笑)。
でも、そうしているうちに選手も慣れてくるというか、対応力が身についてくる。たとえスタメンを外れていても『2番手以降で必ず出番が回ってくるから、きっちり準備しておこう』と集中力を維持したり。そういう意味ではプロフェッショナルになっていきましたよね。なにより95年はその戦いで優勝したので自信になり、日本一になった96年はそれがうちのカラーだと納得するようになっていました」
── その点、今のオリックスは中嶋聡監督の、いわば"我慢の野球"が浸透し、選手たちが花開いたとも言えます。
「まさにそうです。中嶋監督とは2018、19年の2シーズン、彼が二軍監督で僕が打撃コーチという関係で一緒にやりました。その頃から、"我慢"というのをすごく意識していたように思います。長年オリックスは、打者は結果が出ないとすぐ代えたり、二軍に落としたりという状況が続いていました。そんな状況を、中嶋監督は打破したかったんでしょう。そうやって二軍で鍛え上げたのが杉本ら、今年台頭した選手です。使えば必ず結果を出すという手応えもあったのでしょうね。
また今季成功した要因として、中嶋監督の性格的な部分もあると思う。彼は現役時代から信念を曲げないところがある。たとえ監督に就任しても『やることはやる。やるべきでないことは、たとえフロントから言われてもやらない』といった強気な部分があるんです。おそらく納得できないなら、いつでも監督を辞めるといった腹のくくり方をしている気がします。そんな性格が幸いして、選手たちを花開かせたと思うんです」
── 打っても外される"仰木野球"と、打てなくても我慢し続ける"中嶋野球"は対照的ですね。
「そうですね。でも共通しているのは、仰木さんも中嶋監督も信念があるということです。監督がブレないから、選手も安心して試合に臨める。以前のオリックスの打者は、打てなければ代えられてしまうと思うあまり、ベンチを意識しすぎる感があった。敵は相手チームの投手ではなく、ベンチになってしまう。それでは勝てるはずがない。96年の時も今回も、優勝できた要因は戦力のバランスとともに、監督のブレない采配も大きかったと思います」
── これからオリックスはCSファイナル、勝てば日本シリーズが待っています。短期決戦での重要なポイントは。
「短期決戦はいかに調子を初戦に合わせられるかがポイントです。それで一気に決まるといってもいいかもしれない。ただ、それ以上に大事なのはメンタルです。とくにリーグ優勝したチームは『CSは絶対に負けられない』という心理が働き、想像以上に重圧がかかるものなんです。逆に2位、3位のチームは失うものはないと意気込んでくるから、なおさら戦いづらい。そうした重圧に打ち勝つメンタルが必要になります」
── そうした重圧をいかに取り除くかも、監督やベンチの役割になると?
「僕はソフトバンクのコーチとして3回、日本シリーズを経験していますが、それほど仕事はなかった。当時のソフトバンクは、内川聖一(現・ヤクルト)など脂の乗りきった選手が多く、常勝チームと呼ばれていた。選手たちも自信を持ち、戦い方を知っていたから、コーチの役目は彼らを気分よくグラウンドに送り出すことぐらい。
今年のオリックスは25年ぶりの優勝ですし、短期決戦の戦い方を知っている選手は皆無に等しい。当然、ソフトバンクのような真似はできないけど、要はどっしり構えて臨むこと。ベンチは普段の力を出せるよう、いかに環境づくりをしてあげられるかでしょうね」
── 中嶋監督はどんなゲーム運びをすると思われますか。
「じつは、意外と奇策を好むところがあるんです。今年もシーズン最終戦でツーランスクイズを仕掛けましたよね。たまにアッと驚くようなことをするんです。もし日本シリーズに出たら、普通に考えれば初戦は山本由伸でいって、1つ取るのが定石。そこをあえて違う投手でいって、山本を2戦目に使うとか。可能性は低いかもしれないが、なにか仕掛けてくるかもしれません。
いずれにしても、日本シリーズのみならずCSファイナルも山本がカギを握っている。普段のピッチングで勝てば、流れは一気にオリックスに傾くはずです。逆に、山本で負けると痛い。でも、中嶋監督は山本で落とした時、いかに挽回するのかを考えていると思います。『それこそ自分の仕事だ』とでもいうようにね」
■大島公一氏
── 96年優勝当時のオリックスと、現在のオリックス。共通点や違いがあるとしたら?
「当時のチームは、ひと言でいえば大人の集団でした。チームというのは、ひとりのスーパースターだけいても機能しません。中心選手のまわりを固める選手たちが個々の能力に応じた働きをして、はじめてチームになるんだと思います。もちろんイチローみたいな異次元の選手もいましたが、その脇を内野では福良淳一さん、馬場敏史、外野では本西厚博さんといった職人肌の選手たちがいたから、イチローや田口壮ら若手も伸び伸びやれたわけです。いわば玄人好みで、必要な時に点が取れる打線。それが当時のオリックスでした」
── 大島さんは96年に近鉄から移籍しましたが、前年に優勝したチームに溶け込むのは難しかったのでは?
「居場所をつかむには何をすべきか。考えたのは、激しさでアピールすることでした。当時のオリックスはベテランも多く、チーム全体として静かな感じがあった。なので、とにかく声を出し、打っても全力、守ってもカバーリングは100%やる。塁に出ればヘッドスライディングとか。エネルギーが必要だから内心は嫌だったんですけどね(笑)。でも、そうやって元気さ、激しさを前面に出してアピールしなきゃ出番はなかったですからね」
── そんな大島さんを評価して、仰木監督は不動の2番として起用しました。イチロー選手の前後を打つ打者として、難しさはありましたか。
「あの年、イチローは1番か3番での起用だったのですが、僕は3番・イチローの時のほうが好きでした。相手としてはイチローの前にランナーを出したくないから、どうしてもストライク先行の配球になる。甘く入る球も多く、おかげでずいぶんとヒットを稼げました」
── 仰木監督の野球とはどのようなものだったのでしょう。
「仰木監督は当時、猫の目打線で有名になりました。相手投手によって打順を代えるだけでなく、4番打者でもアッサリと外すなど大胆な起用でした。でも、ただ外すだけではなかった。外しても、すぐにチャンスを与えてくれたし、外した選手の代わりには、必ずといっていいほどライバルのような選手を起用していたんです。ライバル心を刺激させ、互いを競わせる。だから選手も必死になる。常に緊張感を持たせるから、選手も腐る暇などなかったわけです。
仰木さんは『1回のミスは仕方ないが、2回目のミスは許さない』というのが持論でした。何度もミスを許してしまうと、チームのためによくないと。選手のことを考えつつ、チーム全体もしっかり見ている監督でしたね」
── 競争と団結を両立するのは難しいものだと思いますが。
「難しくはありません。要は、勝てばいいんです。勝つことでチームがまとまっていくのがプロ野球ですから。もちろん仲のいい選手はいましたが、だからといってベタベタした関係ではなかった」
── 今シーズンのオリックスですが、山本由伸投手、宮城大弥投手の存在が大きかったと思います。
「絶対的なエースがいるのは大きいです。それに、目に見えない貢献もあるんです。たとえば、96年のチームでいうなら星野伸之さん、野田浩司さんという2枚看板がいました。安定した投球ができる2人でしたが、ともにテンポがよかった。抑えている時はもちろん、打たれていてもテンポよく投げてくれた。投手のテンポがいいと打者のリズムもよくなる。結果は負けたとしても、翌日の試合に向けて疲れを残さない。これは大きかった。今シーズンの山本、宮城も成績もさることながら、リリーフ陣や野手に対して好影響を与えていたと思いますね」
── いよいよCSファイナル、その先には日本シリーズがあります。短期決戦の戦いがあるとすればどのようなことでしょう。
「人それぞれ考え方はあると思いますが、出だしを間違えると修正が効かない。だから、とにかく先に攻めていくこと。後手にまわると体って動かなくなるんです。そのためにもどう先手を打てるかを考える。具体的には、初戦の先発投手をイメージして、その投球から狙い球を絞ることもひとつでしょう。
96年の日本シリーズは巨人が相手で、ピッチャーは槙原寛己さんや斎藤雅樹さんなどすごいピッチャーばかり。制球力もよく四球なんて考えられないから、ボールが見えたら振るという意識で臨みました。とにかく受け身になったら、自分のスイングをさせてもらえないと思っていました」
── プロ入り前、社会人やバルセロナ五輪の日本代表メンバーとして短期決戦を経験した立場としては「迷わず攻めろ」ですか。
「勝利を考えがちですが、いかに結果を意識せずにプレーできるか。それはプロアマ問わず、共通した臨み方だと私は思っています」
── オリックスOBとして、今の若い選手たちはどのように映っていますか。
「いい緊張感のなかで選手たちがプレーしているのがうかがえます。吉田正尚という中心打者に、杉本裕太郎、宗佑磨、福田周平が加わったことで、チームはより機能するようになった。中嶋監督が気を配りながら、上手に使っている。絶妙な感じでポジションを与えましたよね。福田はセカンドでポジションを掴むのは難しいかなと思っていたら、センターにまわって生き返りましたからね。宗にしても、これまではいろんなポジションを経験しましたが、どこもパッとしなかった。それがサードで固定したことで、リーグ屈指の守備力を誇る選手になった。
ともにミスもあったと思うのですが、中嶋監督はダメという判断をしなかった。選手も監督を信頼して自信を持って自分のプレーに徹するようになった。福田や宗というのは、監督にとって生かされた好例ですね」
── 当然、選手の能力を理解しているから、このようなことができると?
「チャンスを与えるというのは、選手にとってはうれしいことではあるのですが、プレッシャーでもあるんです。結果を残さないと次がない世界ですからね。監督としても、ただチャンスを与えるのではなく、ちゃんと結果を残せると判断したから起用したと思うんです。そういう意味では、仰木さんと共通した起用法だと思いますね」