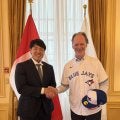サッカー新ポジション論第4回:ディープ・ライング・プレーメーカーサッカーのポジションや役割は、時代と共に多様化し、変化し…
サッカー新ポジション論
第4回:ディープ・ライング・プレーメーカー
サッカーのポジションや役割は、時代と共に多様化し、変化し、ときに昔のスタイルに戻ったりもする。現代サッカーの各ポジションのプレースタイルや役割はどうなっているのか。今回は中盤の底に位置しながら攻撃的な役割を担う選手たちを紹介。ディープ・ライング・プレーメーカーと言う。
◆ ◆ ◆

中盤の底で攻撃的役割を担う、ジョルジーニョ
<スペインでは「クワトロ」>
中盤の中央に位置する選手を大別すると2種類ある。攻撃型か守備型かで、前者はディープ・ライング・プレーメーカー、レジスタなどと呼ばれ、後者はボールウィニング・ミッドフィルダーなどと呼ばれる。国や地域によって呼び方は違い、とくに攻撃型、守備型と分けて考えないケースもある。
場所をそのまま表せばセントラルミッドフィルダーあるいはセンターハーフだが、センターハーフという呼称はあまり使われていない。それは、英語圏でセンターハーフと言えば、センターバックを指すことがあって紛らわしいからだ。
センターバックの元のポジションがセンターハーフだった。2バックシステムからWMシステムの3バックに移行する時代に、中央のハーフバックを3バックのセンターに下げている。そのため英国では1980年代あたりまでセンターバックをセンターハーフと呼ぶ習慣が残っていた。
オランダはこの逆で、日本代表監督などを務めたオランダ人のハンス・オフトは、当時バルセロナでプレーしていたジョゼップ・グアルディオラを「センターバック」と呼んでいた。
当時のバルセロナのシステムは3-4-3、グアルディオラは菱形で組むMFの底でプレーしていたのだが、オランダではこれを4-3-3のセンターバックを前に押し出したポジションと見ていたのでセンターバックなのだ。
現在は名監督として知られるグアルディオラは、深い位置にいる攻撃型MFの代表格だった。スペインでは「クワトロ」とも呼ばれる。
3-4-3の中盤の底が「4番」なのは、オランダ方式の呼び方だ。後方右側から機械的に背番号をつけていくオランダ方式では4バックが右から2~5番。センターバックの4番を1つ前に出したので中盤の底が「4番」というわけだ。
ちなみに4-3-3での中盤の底は6番だが、バルセロナの3-4-3ではトコロテン式に6番が前に押し上げられて、トップ下の背番号になっていた。
グアルディオラは3番をつけてプレーすることが多かった。4バックから上げたポジションなので3番でも4番でもいいわけだが、なぜかこのポジションの呼称は「クワトロ(4)」になっている。
<チームの色を決めるポジション>
グアルディオラがプレーしていた時のバルセロナのヨハン・クライフ監督は、テレビのインタビューで「クワトロ」を最重要ポジションと言っていた。
フィールドを模した緑色の布のセンターサークルにコマを置き、「ここが最も重要だ」とバルセロナの戦術を語りはじめる。その時、フィールドの自陣側半分ほどは布を手前に引き寄せてしまったためにテーブルから垂れ下がっていた。
GKもDFも置かず、いきなり「クワトロ」から話をはじめたのはクライフらしく、同時にこのポジションの特徴とは何かがよく表れていた。
ディフェンスラインの10メートルほど前の中央。ここにボールを奪うのに長けた選手を置くか、攻撃の構築に優れたタイプを起用するかで、チームのカラーが決まってくる。
クライフ監督が率いたバルセロナは、攻撃するためにここにプレーメーカーを起用した。当初はルイス・ミジャやロナルド・クーマンが起用されたが、下部組織にいたグアルディオラを引き上げ、その時に3-4-3の骨格が定まっている。
ボールを保持して攻撃するには、自陣から確実にパスをつながなければならない。そのためにディフェンスラインと前方を連結するポジションに、パスワークに長けた選手を起用した。
グアルディオラは線が細く、守備が強力なタイプではなかったので不安視する声もあったが、クライフ監督にとっては攻撃こそ最大の防御という理屈なので、「クワトロ」は攻撃力に優れた選手が必須だった。
深い場所に鎮座するディープ・ライング・プレーメーカーはクライフの発明ではない。1960年代のインテルはカテナチオで有名だが、ルイス・スアレスが深い位置から攻撃を操る役割を担っていて、イタリアでは「レジスタ」として受け継がれていった。
スペインで「クワトロ」の伝統を引き継ぐ代表格が現在のセルヒオ・ブスケツ(バルセロナ)であり、前所属のバイエルンでチャンピオンズリーグ優勝の原動力だったチアゴ・アルカンタラ(リバプール)がいる。少し前にはシャビ・アロンソが活躍した。
イタリアの「レジスタ」はジョルジーニョ(チェルシー)、マルコ・ヴェラッテイ(パリ・サンジェルマン)が活躍中で、その前にはアンドレア・ピルロが代表格だった。
ディープ・ライング・プレーメーカーは、アメリカン・フットボールのクォーターバックと似ている。ラグビーならスタンドオフ。最後方ではないが後方に位置していて、そこでボールを預かって攻撃の起点となる。
前方のアタッカーほど厳しくマークはされないので余裕はあるかわりに、絶対にミスしてはいけない。的確にパスを散らしつつ、チャンスがあれば一発で急所を突くロングパスの精度も求められる。
ここに、このタイプの選手を起用する以上、ボール支配率を高めてより多く攻撃する意思がチームとしてなければならない。長い時間守るなら、守備力のある選手を使ったほうがいいのは自明である。攻撃する、パスをつないで押し込む、そのためのポジションだ。
<フィールドの指揮者>
1980年代にローマでディープ・ライング・プレーメーカーだった、ブラジルのパウロ・ロベルト・ファルカンについて、当時のニリス・リードホルム監督はこう話している。
「彼はオーケストラの指揮者だ。(監督としての)私の仕事は、彼のために楽曲を提供することにほかならない」
監督とディープ・ライング・プレーメーカーは一心同体な関係になりやすい。ジョルジーニョはいまだに「サッリの息子」と呼ばれている。マウリツィオ・サッリはチェルシーで1シーズンしか監督をしていないが、ナポリから連れてきたジョルジーニョは戦術的に不可欠な存在だった。
2000年代のミランでピルロをこのポジションに起用した、カルロ・アンチェロッティ監督も同様。ただ、ジョルジーニョもピルロも、監督が代わってもチームで重用され続けた。クライフが去ったあとのグアルディオラもそうだった。
中盤の底にプレーメーカーを起用するのは勇気がいる。きっかけを与える監督は、選手と心中するぐらいの覚悟が必要なので、きっかけは決定的だ。ただし、いったんその価値を示したあとなら、誰が監督になってもアンタッチャブルな存在になる。すでにチームの色が決まってしまっているからだ。
最初に楽曲を渡す監督はいるが、そのうち指揮者に合わせた曲が演奏されるようになるのだ。