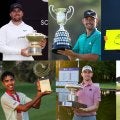なでしこジャパンの東京オリンピックは、決勝トーナメント1回戦でスウェーデンに敗れ、ベスト8という形で幕を閉じた。 後半…
なでしこジャパンの東京オリンピックは、決勝トーナメント1回戦でスウェーデンに敗れ、ベスト8という形で幕を閉じた。
後半のアディショナルタイムの表示は5分。3失点している日本が抱える得点差は2。誰もが敗戦を覚悟して見守る中、選手たちは最後までボール奪取に全走力をささげ、ボールを要求し、ゴールを目指していた。その姿からは「まだ何かできるはず」という想いが伝わってきた。それでも残り5分はあっという間にすぎていった。1−3。東京オリンピック最後の戦いは完敗だった。

スウェーデン戦後、涙を流しながら成長を誓った清水梨紗
この準々決勝は、高倉麻子監督が就任してからのすべてが凝縮された試合だった。約5年間という月日を経て、臨んだ東京オリンピック最後の試合ですべての課題が明確になった。ベスト4に駒を進めたチームは日本を下したスウェーデン、オーストラリア、アメリカ、カナダ。スウェーデン以外は延長戦もしくはPKにまでもつれ込んだ大接戦の末の勝ち上がりというかつてないほど熾烈なノックアウトステージとなった。この結果から見ても、残念ながら日本が一段格落ちであることを認めざるを得ない。
世界との差はどこにあったのか。まず筆頭に挙げられるのは、最悪の立ち上がりだろう。この試合では最もこの悪癖が表面化してしまった。3失点中2失点は前後半立ち上がりに食らったもの。全試合で言えば、イギリス戦での1失点以外、すべてが前後半開始10分までの失点だ。これではゲームプランは早々に崩れてしまう。高倉監督下において常に抱えてきた課題だが、最後まで克服することはできず、致命的だった。
準々決勝は19時からの開始。日中の厳しい暑さを溜め込んだピッチに水がまかれ、前半は蒸し風呂のような高湿度下でのプレーとなった。後半にスウェーデンの選手の動きが落ちた要因の一つはそれで、日本はイーブンでその時間帯に持ち込んで、勝機を見出す計算があったはずだ。けれど、その時間帯に入るまでにすでに2点のビハインドがあってはどうしようもない。
決して選手たちの気が緩んでいた訳ではない。
「集中しろ」「ボールに行け」「ラインを上げろ」
自覚があるからこそ、ピッチ上では様々な声が飛んでいた。にもかかわらず、やられてしまうというところに精神論ではない問題点がある。相手は100%日本の立ち上がりを狙ってくるのだから、具体的な対応策を持てなければ未来永劫苦しめられることになるだろう。
そしてもうひとつ、高倉監督の最大の誤算は最も力を入れてきた"日本らしいパスサッカーで崩す攻撃"が鳴りをひそめてしまったことだ。当然のことながら相手はそのパスを出させまいとプレスをかけて出どころを潰していく。出せたとしても飛距離とスピードがない日本のパスでは、2手目、3手目で潰されてしまうことが多い。
常に相手の逆を突き続けなければパスが通らないことを実感させられた。スウェーデンはそこを無駄に追わず、ある程度日本にポゼッションを"譲った"上で効果的に攻撃を潰していく手法を織り交ぜていた。暑い中では正しい省エネプレーだった。
ただ、日本の攻撃がうまくいった場面もあった。得点した前半23分。最終ラインの熊谷紗希(バイエルン・ミュンヘン)から右サイドの清水梨紗(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)へ、そしてその前へラインを取った長谷川唯(ACミラン)へとつなぐと、長谷川は相手DFラインの裏へボールを放り込む。
田中美南(INAC神戸レオネッサ)がわずかにスウェーデンに走り勝って合わせた。小気味よく細かいパスを1タッチのプレーで崩してという理想的なものではないが、日本がオリンピックという舞台で強度を上げた一つの形だ。それぞれが少しずつ伸ばして磨かれたものが、最後に田中を競り勝たせるわずかな時間を生み出した。
このゴールにも絡んでいたのが清水。彼女が頻繁に駆け上がったことで日本は何度も好機を生んだ。熊谷が控えているとはいえ、持ち場を離れて何度もアップダウンを繰り返すことは容易ではない。清水から長谷川につなぐ時により効果的だったのが、ダイレクトパスだった。長谷川が阿吽の呼吸で走り出す。2人によって組み立てられた攻撃は最もゴールの香りを漂わせた。
後半には、清水自ら中へワンツーをもらいに走り込み、思い切りシュートを狙った場面もあった。彼女に限っては、相手が強豪・スウェーデンであることを感じさせないプレーを貫いていた。それでも、2失点目は、自身が振り切られて決められていたことで、彼女の涙も止まらなかった。
2019年のプロ契約をきっかけにフィジカルトレーニングにも取り組んできた。
「ヒョロヒョロだったので吹っ飛ばされることも多かった」(清水)
それでも「相手を消すサイドバックになりたい」とワールドカップで痛感した1対1の強度にも取り組んできた。上々の仕上がりで臨んだが、やはり世界は強かった。
「世界のサイドハーフはレベルアップしてきてる。そこを自分が止めるか止めないかで勝敗に関わってくるというのをこの大会を通じてすごく思いました。対人能力はもっともっと高めていかないといけない」
清水は涙の中にもさらなる成長を誓った。
試合後、高倉監督はなでしこジャパンに対する「気迫が感じられない」「勝負していない」といったマイナスな意見が噴出していることを受けて、「なかなか闘志が前面に出るタイプの選手が少ない中で、いろんな声がありましたが、選手はこの大会中、本当にすべてを懸けて戦っていた。その点に関してはたたえたい」と選手たちをねぎらった。
闘志がないはずがない。それは試合後の選手たちを見ていればわかる。覚悟はしていても、オリンピック最後のホイッスルは、選手たちの気丈さを崩壊させた。一時同点弾を決めた田中は膝から崩れ落ち、岩渕真奈(アーセナル)はゆっくりとスピードを落とすと、終了とともに動きを止めたボールに触れた。それぞれに抱えていたものが目標とともに崩れ落ち、涙を溢れさせた。キャプテンの熊谷は現状を真正面から捉え、こう語った。
「チームとしてやれることはぶつけたつもりでいます。ただ、2019年のフランス・ワールドカップの負け方と今日の負け方を考えた時、自分たちがうまく支配できて、相手の嫌なプレーができていたか、怖いプレーができていたか、結果を残せたかというと......。これが今の世界との本当の差だと思います」
そして、熊谷は声を詰まらせながら、こう言葉を絞り出した。
「これから世界で勝っていくために......、何をしていかなければいけないのか、もう一回考えるべきだし、うまいだけで勝てる相手ではない。自分たちのウィークな部分をどれだけ戦えるまでにしていくかが、日本女子サッカーの課題だと思います」
闘志はあるが、それが見ている人には伝わらない。世界を制した2011年以降、常に結果を求められてきたなでしこジャパン。世代交代の波の中で、この期待値とイコールに持って行く力が及ばなかった。歯がゆく、もどかしくそして何よりも悔しい想いをベテランはしているはずだ。そして若手はこの悔しさが経験値となり、殻を破っていくための糧を得た。このオリンピックのすべてが必ず今後のなでしこジャパンの原動力になる。今はそう信じて前を向くしかないだろう。