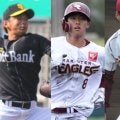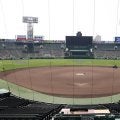「令和に語る、昭和プロ野球の仕事人」 第19回 長池徳士・前編 (記事一覧を見る>>)「昭和プロ野球人」の貴重な過去のイ…

「令和に語る、昭和プロ野球の仕事人」 第19回 長池徳士・前編 (記事一覧を見る>>)
「昭和プロ野球人」の貴重な過去のインタビュー素材を発掘し、その真髄に迫るシリーズ。美しいフォームのアンダースロー投手を取り上げた前回に続き、今回はモノマネしやすい打撃フォームで知られた長池徳士(ながいけ あつし、1978年までは徳二・とくじ)さんにフォーカスする。
阪急ひと筋の現役生活を送り、本塁打王と打点王が3回ずつ、ほかにも打撃部門で数々の記録を打ち立てた実績を誇る長池さん。その輝かしい球歴の割には伝わる機会の少なかった肉声をもとに、昭和を代表する強打者の実像を探りたい。

アゴが肩に食い込む長池徳士の独特な打撃フォーム(写真=時事フォト)
* * *
長池徳士さんに会いに行ったのは2011年6月。その前月、オリックスが前身球団=阪急ブレーブスのユニフォームを復刻した。着用してプレーするナインを見ていたら、小学生の頃、阪急が日本シリーズで三連覇したときの記憶がよみがえった。長池さんは[ミスター・ブレーブス]と呼ばれた4番打者だった。
三連覇は1975年に広島、76年、77年と巨人を倒して達成された。当時の僕は阪急の本拠地・兵庫から遠く離れた東北に住む巨人ファンだったが、パ・リーグ優勝チームの強さを痛切に感じていた。そのなかで長池さんが印象的だったのは、打撃フォームによる。
右打席で左腕を大きく捕手側に引き、左肩にアゴを乗せる独特の構え。野球好き仲間の間で、「ナガイケ!」と言ってからその真似をするのが流行り、巨人の王貞治=一本足打法の真似に次いで人気があった。が、当時の東北でパ・リーグの試合を観る機会はテレビでも滅多にない。
だから長池さんといえば「阪急の4番」というだけで、どんな選手だったのか、詳しく知らないまま大人になってしまった。野球の取材をするようになってからも、知識はプロフィール程度。それが復刻ユニフォームをきっかけにあらためて興味を持ち、資料に当たろうとしたところ、関連の文献が少ない。意外だった。
何しろプロ14年間で通算338本塁打、969打点を記録し、本塁打王3回、打点王3回、MVPを2回獲得した名選手。パ・リーグ記録の32試合連続安打も達成している。まして、引退後は5球団でコーチを務めた方だけに、著書があって当然とも思えるが、それもないのは何故か──。そんな興味も持ちながらインタビューを申し込んだ。
取材場所は兵庫・宝塚市の阪急線沿線、宝塚大劇場から程近いホテル。約束の午後2時より15分早く着いたが、年配の観光客で混み合うロビーに鮮やかなチェリーピンクのシャツがひときわ目立っていた。待合席で携帯電話に視線を落とすその人が長池さんで、歩み寄ると僕の電話の着信音が鳴った。
パッとこちらを見て立ち上がった長池さんは、「今ちょうど電話したところです」と言って笑った。上背はあまりないものの、肩幅広くがっしりとした体格。67歳という年齢(当時)を感じるのは白髪まじりの頭髪だけで、自然光がふんだんに入り込むカフェレストラン、窓際の席で面と向かうと、引き締まった風貌が余計に若く見えた。
取材主旨を説明し、高校時代にエースで4番だった話から切り出すと、長池さんは身を乗り出し、ピッと背筋を伸ばして言った。
「当時はピッチャーでしたね。それで甲子園、センバツに出たのは柴田勲の法政二高が優勝したとき。昭和36年ですか。そのとき僕、選手宣誓をやったんですよ」
エースで4番で、キャプテンでもあった長池さん。それにしても、甲子園で選手宣誓を経験したプロ野球選手、あまり聞いたことがない。
「数少ないと思います。大変光栄だったですねえ。今思えば、なかなかできないことで」
徳島出身の長池さんは2歳年上の兄の影響で野球を始め、その兄が野球部のキャプテンを務める撫養(むや)高(現・鳴門渦潮高)に進学。1年時の秋に野手から投手に転向し、センバツ出場を契機に南海(現・ソフトバンク)のスカウトの目に留まることになる。当時の鶴岡一人監督にも直に誘いを受けたという。
「夏の大会の予選が終わって、鶴岡さんとコーチの方にピッチングを見てもらいました。そしたら『今はプロでは使えない。4年ぐらいかかるから。大学へ行ってこい』って言われて、僕、法政へ行ったんですよ」
東京六大学の法政大に進学した長池さんだったが、肩を壊した影響で早々に投手を断念。捕手か内野に転向することになったとき、「キャッチャーやるなら神宮の試合でユニフォーム着せてやる」と監督に勧められた。
「でもね、1年生ですから。キャッチャーやるとピッチングばかり受けて、バッティング、さしてもらえないんですよ。だから『キャッチャーはやりません』って言って。『いやだ』って断ったんです」
急にやるせないような表情に変わっていた。1年生にして果敢に指導者にわがままを言えたとは痛快な話ではあるが、しかし、一言で断れるものなのだろうか。
「断ったの。それで内野をあちこち行ったけど、うまくいかない。『じゃあもう、好きなとこ行け』って言われて外野に行きました」
監督の意向を平気で断り、守備位置の自由を与えられたのも、バッティングで結果が出ていたからだったのか。
「いや、そうじゃなかったですねえ。新人戦で、僕、ホームラン2本打ったんです。それが認められて、1年生の秋からベンチに入れてもらいましたけど、結局は全然打てなくて。結果が出たって言ったら、3年生の秋、首位打者を獲ったときですかね」
実際、大学時代の長池さんの目立つ勲章は首位打者だけで、4年間の通算本塁打数は3本。プロ入り前は長距離砲ではなかった。
「そのうち、僕が4年生のとき、ドラフト制度がカチャンとできた。僕は南海へ行くつもりでずっとやっていたわけですけど、とにかくプロ野球選手になりたかったので、リストアップしてくれた阪急に行こうと」
1965年の第1回ドラフト、長池さんは阪急から1位で指名された。獲得を決めたのは当時の西本幸雄監督。ある日、法政大のエースの投球を見に訪れたところ、長池さんの打球の速さに目を奪われたという。
その時代の阪急は投手陣の駒が揃っていた半面、打線が弱かった。65年も石井茂雄、米田哲也と20勝投手を二人も出しながら、チーム打率はリーグ5位で、順位は前年の2位から4位へと下降。そこで、新人補強においては、打撃に魅力ある長池さんを獲りにいったのだ。
「確かに、ピッチャーは揃ってましたけど、打つ人がスペンサーしかいなかったですからね。そこで西本さんの考えは『将来、長池を4番にしよう』と。そういう意図で、僕を1位で獲ったと思うんです。もちろん、今思えばの話ですよ。で、当時のヘッドコーチ兼バッティングコーチが青田さんです」
大学時代にわずか3本塁打の長池さんを4番打者にすべく、打撃指導を施したのが青田昇だった。現役時代の青田は巨人、阪急、洋松、大洋(現・DeNA)で活躍し、首位打者1回、本塁打王5回、打点王2回獲得の強打者。数少ないどの資料にも、〈僕は作られた4番バッターなんです。青田昇によって〉という長池さんの言葉が載っている。
「最初、2月のキャンプのとき、西本さんと青田さんが教えてくれるわけですけど、当然、二人から教えられると言葉遣いもニュアンスも違うし、教えるポイントも違う。同じ内容を言っても表現の仕方が違う、っていうこと、よくあるじゃないですか?」
まさに、これまでの野球人取材で何度となく、同様の話を聞いてきた。大半がバッティング指導における話だった。
「そうでしょう? 僕はもう大学から入ったばっかりで、頭ん中、空っぽの状態で聞いているのに、こんがらがってきてわからなくなるんです。だから僕、『二人から言われたらわからんから、どちらか一人にしてくれ』って西本さんに言ったんですよ」
またもや、指導者に対する果敢な発言。これはわがままではないにせよ、新人選手がそこまで監督にきっぱり言えるものだろうか。しかもまだ2月のキャンプ時であって、プロで何の実績も残していない段階なのだ。なかなかできることではないだろう。
「ああ、今思えば、そうですねえ。でも僕、わからんから言ったんですけどね。そしたら西本さんが『青ちゃん、頼むで』と言って、僕を青田さんに預けた。ただ、今みたいにマンツーマンじゃないんですよ。例えば、『見とけ!』って見本を見せられて、それだけなんで、見たってわかりません。懇切丁寧に手取り足取り教えてくれない。パパッと一言で終わりなんですから」
腕組みをしてじーっとこちらを見据え、長池さんは「終わりなんです」と繰り返した。結局、わからないままに自分で練習するしかなかったようだ。
「もう当然、自分でやるしかない。ただ、青田さんに言われた一言によって、僕が成功したのは確かなんです。僕、インコースが打てなかったんですね。スピードについていけなくて、とにかく前へ飛ばない。その打ち方を青田さんが教えてくれた。弱点、欠点が、逆にその一言で長所になったんですよ」
くっきりと白い歯が見えていた。これまでになく言葉に力が込められている。青田コーチはどう表現したのだろうか。
「とにかくボールの内っかわから自分の手を出せ。その一言。結局、青田さんはゼロから1、2、3、4、5と教えてくれない。いきなり10から始まって、9、8と。終点から先に来るんです。だからインコースの打ち方も実際にはわからなかったんですが、僕をスカウトしてくれた藤井道夫さん。この人が、ああいう表現の仕方は実はこうなんだ、と説明してくれたんです」
担当スカウトがコーチに選手の性格を伝えたり、選手の面倒を見て現場でアドバイスしたりすることは今でもある。それにしても、長池さんのように「表現の解説」が必要だったケース、過去にどれぐらいあっただろうか。もしも藤井スカウトがいなかったら、成功まで時間がかかったかもしれない。
「確かに、そうですねえ。1年目、二軍にいるとき、藤井さんはいっつも来てました。僕、開幕は一軍だったんですけど、2試合に出て、全然打てなくて。で、明くる日から7月のオールスター明けまで二軍。その間に7本ぐらいホームラン打ってると思います」
二軍では十分に通用していた、ということかと思いきや、長池さんは否定した。
「今考えたら二軍は遊びみたいなとこでね。当時は一生懸命やったんでしょうけど。で、二、三度、お呼びがかかったんですよ。『一軍に上がれ』って。でも、僕はずーっと断ってたんです」
新人が、一軍昇格の要請を断る? いや、新人じゃなくても断る選手はいないだろうし、第一に断る理由が見つからない。大学時代に捕手を断って、プロ入り直後にコーチ二人体制を断って、我を通してきた長池さんらしさ、なのかもしれないが、こればかりはあまりの衝撃に言葉が出ない。
「だから藤井さんがいっつも来て、『一軍に上がれ』と。結局、オールスター明けの7月23日かな、『区切りで、もうおまえ一軍に来いよ』って言われて。『それじゃあ行きます』って。南海戦で、僕、ピンチヒッターで出て、渡辺泰輔さんからプロ入り初安打」
長池さんのなかでは、機が熟すまで一軍には上がらない、満を持して上がる、という考えがあったのか。それとも、まだまだ自信がないから上がらない、ということだったのか。
「いやどうなんでしょうかねえ。あんまり、行きたくなかったんじゃないですかね。ただそれだけじゃないですか? はっはっは。普通は、喜んで行きますよね、お呼びがかかれば。僕は違いましたね」
普通との違いを自覚した上での発言になおさら戸惑う。およそ、今も昔も、プロ野球の世界でありえない話を僕は今聞いている。
「特別な理由はなかったと思います。断ったといっても、当時は今ほどね、はっきりした通達はなかったですから」
たいていの伝説めいた逸話には時代背景が付き物だ。が、僕は「そういう背景があったんですね」と言いながらも納得はできなかった。しかしこれ以上は何も言えない。
「で、明くる日も当然、南海戦で、巨人から移籍してきた高橋栄一郎さんから初ホームラン、初打点。そこから僕、ずーっと後半40試合ぐらい出たんですかね。2割7分ぐらい打って、ホームラン7本打ってるはずです」

精悍な風貌は現役時代と変わらない、取材当時の長池さん
プロ1年目、66年シーズンの長池さんは、チームが5位に終わったなかで計68試合に出場して打率2割6分3厘、7本塁打。翌67年には一気に27本塁打と大ブレイクし、打率は2割8分超え。若き4番として、阪急の初優勝に大きく貢献している。青田コーチの指導、藤井スカウトの援護があって、早くも4番に座ったと言えそうだ。
「数字を残せて、まあまあ、自信はできましたね。それと、スペンサーからいろいろ盗むところ、教わるところもありね。彼が3番にいて、僕を楽にしてくれて、助けてくれた。だから、4番の座を守れたのはスペンサーがいたからです。"スペンサー・メモ"を盗み見して、そこから僕なりにアレンジして、ずいぶん役立ちました。僕の数字はもうそれに尽きるんじゃないですかね」
当時、阪急に在籍した助っ人、ダリル・スペンサーによる"スペンサー・メモ"。それはいったいどのようなものだったのか。
(後編につづく)