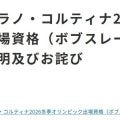川崎フロンターレACLウズベキスタン紀行@03 川崎フロンターレとガンバ大阪はウズベキスタン、名古屋グランパスとセレッソ…
川崎フロンターレACLウズベキスタン紀行@03
川崎フロンターレとガンバ大阪はウズベキスタン、名古屋グランパスとセレッソ大阪はタイでの集中開催で行なわれたAFCチャンピオンズリーグ(ACL)2021の東アジア地区グループステージが7月11日に閉幕。タイトなスケジュールを戦い抜いた結果、グループGの名古屋、グループIの川崎、グループJのC大阪が決勝トーナメント進出を果たした。Jリーグで圧倒的の強さを見せる川崎の選手たちが異国の地でどんな日々を送っていたのか、約3週間のウズベキスタン遠征をレポートする。
「川崎フロンターレACLウズベキスタン紀行@01」はこちら>>
「川崎フロンターレACLウズベキスタン紀行@02」はこちら>>
※ ※ ※ ※ ※

ハットトリックを達成したレアンドロ・ダミアン
ウズベキスタンにて集中開催で行なわれていたACL東アジア地区グループステージで、川崎フロンターレは6連勝を飾って無敗で決勝トーナメント進出を決めた。
7月9日に行なわれた第5節の大邱(テグ)FC戦は、レアンドロ・ダミアンのハットトリックで3−1と勝利。グループステージ突破をかけた大一番を制し、第5節まで全試合に出場してきた脇坂泰斗は安堵感をにじませた。
「昨年Jリーグのタイトルを獲って、今年もJリーグを制すると同時に、アジアの舞台でもフロンターレが引っ張っていこうという目標も掲げてシーズンをスタートしました。そこに一歩近づくことができて、まずはホッとしています」
1−1で迎えた54分には、家長昭博が抜け出した折り返しに走り込むと左足でシュート。56分にも三笘薫の縦パスから決定機を迎えた。
「2本あった決定機を決め切れなかったのは自分の力不足。もっと上に行くためには、あそこで決めて、チームを勝たせられる選手にならなければいけないと思っています」
脇坂はそう言って猛省したが、決勝点となった64分のゴールは彼の好プレーから生まれた。ゴール前でボールを受けた脇坂は相手に奪われそうになるも、再び追いかけるとボールを突いてレアンドロ・ダミアンへとつないだ。
「あの得点シーンは攻撃と守備がぶつ切りにならずに、連続した動きで奪い返しに行ったことで得点につながりました。ゴールになったのはダミアンのおかげですけど、そうした意識がゴールを生んだと思っています。
大邱はボールを蹴って、それを競って、拾って攻める特長がありました。それもあって、監督をはじめ選手全員が前線からの守備を意識していた。相手に長いボールを蹴らさないように、前線から守備をすることができれば、自分たちが下がることもないし、その一瞬を頑張ることで結果的にチーム全体が楽になりますからね」
第4節までロコモティフスタジアムで戦ってきた川崎にとって、プニョドコルスタジアムで試合をするのは第5節の大邱戦が初だった。中2日の連戦で使用され続けてきたピッチは、画面越しでも凹凸がわかるほど荒れていた。いかなる環境でも戦い方を模索し、勝利できたことは成長と言えるだろう。
「気温は高いけど湿度は高くないので、夜は少し涼しいと感じられる環境でプレーしていたのですが、大邱戦の会場はまったく風が通らず水も撒いていたので、日本の夏場のような蒸し暑さがありました。
5試合目ということで芝も荒れていたので、自分たちが思うようなサッカーができないことはアップの時からわかっていました。そうした状況に惑わされずこれまで積み上げてきたように、1勝を目指した結果が勝利につながったと思います」
クラブのSNSでは練習時の気温が42.9度を示す写真が紹介されたが、環境に慣れるところからウズベキスタン遠征はスタートした。
「湿気はないですけど、暑いは暑いですよ。試合日にメンバーに入らなかった選手たちは午前中に練習しているのですが、日中はとくに灼熱だと言っていました。普段の練習も夕方の5時、6時から始まるのですが、とにかく陽射しが強いんです。
ちょうど太陽も降りてくるので、余計に眩しさと暑さを感じます。気候的には、乾燥しているので喉がカラカラになるんです。今は慣れてきましたけど、サッカーをしている時は口を閉じることができないので、当初は喉がしまらないような感覚になりました」

中2日の6連戦は
「経験ない」と語る脇坂泰斗
コロナ禍により集中開催で行なわれたACLは「中2日の6連戦」という過密日程だった。「さすがに経験したことはなかった」と、脇坂は苦笑いを浮かべる。
「やっぱり3、4試合目くらいからはきつくなってきました。でも同時に、連戦に慣れてきた感覚もありました。ただ、連戦に慣れて頭のほうはクリアになっていくんですけど、どうしても体力的な疲労を感じるので、リフレッシュの仕方は大事にしていました」
選手たちが異国の環境に慣れ、過密日程を戦い抜けるようにと、コンディション面で尽力してきたのがフィジカルコーチの篠田洋介だった。豊富な経験を持つ篠田にとっても、「これだけ中2日の連戦が続く経験はなかった」と話す。
「開催地がウズベキスタンに決まってからは、ほかのスタッフたちも含め情報収集を進めてきました。調べた結果、熱くて、乾燥しているということがわかったので、選手たちがこっちに着いてから慌てることがないように、時差や気候について情報を伝えました。
たとえば、乾燥しているからリップクリームを持っていったほうがいいとか、ホテルの部屋はさらに乾燥しているから持ち運べるような小型の加湿器を持っていったほうがいい、という情報も事前に伝えました。日常生活を送るうえで、なるべく選手たちがストレスを感じないように、心の準備というものも大切になりますからね。
ほかには、乾燥しているから、練習中にガムを噛むことで喉の渇きを押さえるようにしたらどうか、とアドバイスもしました」
ウズベキスタンに到着してから初戦まで、6日間の調整期間があったことも大きかったと篠田コーチは振り返る。
「こちらの気候と環境に選手たちが慣れる時間があったことが大きかったですね。鬼木(達)監督をはじめ、ほかのコーチングスタッフの理解もあって、最初の2日間はレクリエーションをメインにして、身体を起こすことに特化できました。
それによって、残りの4日間で初戦に向けてコンディションを上げていくことができました。海外遠征に来ると少し体調を崩してしまう選手もいるので、調整する時間があったのはかなり大きかったと思います。試合がはじまり、中2日の連戦になってからは、ある程度出場時間を考慮しながら、次の試合、次の試合と準備できました。
試合翌日は大きく2つのグループに分けて、試合に長く出た選手は少し身体を動かしてリカバリーする。もう一方のグループは、次の試合に向けてコンディショニングを上げていく。そうした状況が作れたのも、フロンターレには信頼されている選手が多くいるので、試合ごとにチーム全体をうまく回すことができた結果だと感じています」
3戦目が終わったあとには、選手たちの疲労を鑑みて、トレーニングというよりは遊びの要素を取り入れたミニゲームなどを行なうことで、選手たちの心身をリフレッシュさせる時間を作ってもらったと篠田コーチは話す。フィジカルだけでなく、メンタルにも目を向けながらの6連戦だった。
「コンディション作りに関していえば、持ってくるものは本当に必要最低限だったのですが、幸い施設にはジムがあったので、こちらを有効活用させてもらいました。プールや卓球台もあったので、制限があるなかでも使えるものを上手に使って、選手たちにリフレッシュしてもらい、身体の回復についても取り組んできました。
クラブハウスにいれば、それこそ交代浴ができたり、クライオセラピーができたりするのですが、こちらではそれはできない。ならば、ホテルに頼んで氷をもらってきて、それをバスタブに入れてアイスバスの代わりにする。スポンサーである『BARTH』から提供してもらった入浴剤を活用して選手の疲労回復を促したことも、そのひとつです。
練習時間も1時間半と限られていたので、できないことはできない。だからこの状況下で、何ができるかを常に考えて取り組んできました」

プールを使ってコンディションを調整するジェジエウ
もともと喉が弱かったこともあり、脇坂はまさに加湿器を持ち込んでいたひとりだった。
「寝るときは加湿器に加えて、濡れタオルも干してダブルで対策していました。びしょびしょすぎるかなって思うくらいタオルを濡らしているんですけど、朝起きるとカラッカラになっているんですよね。ちょっとそれには驚きました(笑)。
ガムについては、自分としてはプレーしにくいところがあったので、1日やってみたうえでやめました。トレーニング後に身体を冷やすことができずに最初は困りましたけど、氷を使わずにシャワーを水にして対応したり、プールで身体を冷やしたりしました。だから僕の感覚としては、何とかなるんだなって。
日本にいる時とは確かに違いますけど、そこでどれだけストレスを感じないようにできるかが大事。それには常日頃からシノさん(篠田)をはじめ、いろいろな人にアドバイスをもらい、試してみて自分自身で取捨選択していくことをしていました。あらためて、そこが大事なんだなと思いました」
選手全員はもちろん、スタッフも含めた総勢55人でウズベキスタンに乗り込み戦ったACLで、チームとして成長した部分はあるかと聞けば、脇坂は首を横に振った。
「チーム全員でウズベキスタンに来られたのは、間違いなくフロンターレにとってポジティブで、それがうまく出せたグループステージだったと思います。でも、この大会に来てチームが成長したとか、総合力が上がった、ということはないというか。もともと、持っていたチームとしての層の厚さ、常日頃からやっているひとりひとりの意識の高さが出た結果だと思っています。
若手の追随を許さない先輩方、そこに着いていこうとする年下の選手たち。それを支えてくれる監督やコーチといったスタッフの人たち......いろいろな人の気持ちがひとつになっているのが、フロンターレだと僕は思っているんです。だから、ACLに来て変わった、成長したということはなくて、本来持っていた力をここで見せられた期間だったかなと思っています」
誰が出ても、川崎フロンターレ。グループステージを振り返れば、脇坂の言葉に深くうなずいた。
日本に帰ってからも、コロナ禍のため、しばらくはバブル方式での生活が続くことになる。それを脇坂に問いかけると、こう言って笑った。
「家にはまだ、しばらく帰れないかもしれないですけど、僕としては日本に帰れるだけでハッピーです」
ウズベキスタン遠征を通じて、「チーム川崎」の一体感を知ると同時に、そのひと言が過酷な日々を物語ってもいた。そして、彼らの戦いは続いていく。