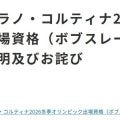じめじめとした梅雨入りの季節に、浮かない気持ちをからっと晴らしてくれるのが、試合前とハーフタイムにおこなわれる、チアリ…
じめじめとした梅雨入りの季節に、浮かない気持ちをからっと晴らしてくれるのが、試合前とハーフタイムにおこなわれる、チアリーダーのはつらつとしたダンス・ショーとスプリンクラーの散水だ。初夏のスタジアムでは、つやつやと水を含んだ芝生のうえを通って吹く涼しげな風が心地いい。FCバルセロナで、パススピードを上げるためにヨハン・クライフが始めた散水が、いまではスタジムで四季を過ごすこの国のサッカー観戦者を楽しませている。
■埼スタ、柏スタジムの散水は日本基準
ワールドカップでは、1998年フランス大会の一部のスタジアムでは「水芸」が行われていたが、2002年日本・韓国大会では使われなかった。日本のスタジアムで最初に埋め込み式のスプリンクラーを設置したのは、カシマ・スタジアムだったという。
スプリンクラー設置は、ピッチの全面改修に合わせて行われる。埼玉スタジアムでは両タッチライン、両ベンチのすぐ横に計4基の放水機があり、そこから大きなアーチを描いて放水が行われている。勇壮な光景だが、この方式ではピッチ全面に均等に水がまけるわけではなく、どうしてもムラが出る。近くピッチが全面改修されるとのことで、ようやく埼スタも念願の「水芸スタジアム」の仲間入りができるようだ。
三協フロンテア柏スタジアムでは現在の埼スタのような設備もなく、長い間消防用のホースのようなものをつなぎながらピッチの中央まで引っぱっていって散水していた。まずクルクルと巻いてあるホースを伸ばしながら引っぱっていって何本かつなぎ、散水する。そして終わるとホースを巻き取りながら片づける。当然ながらホース内には大量の水がつまっているので、巻き取るとつなぎ目を外したところだけはかなりの量の水を吸い込むことになるのである。ここまでして水をまく必要があるのかと、その大変な作業を見ながら、私は何回も思ったものだった。
そしてより奇妙なのは、ボールのスピードを上げ、試合のレベルを向上させるための散水であるはずなのに、Jリーグでは、ボールならぬ自分の足を滑らせ、転倒してしまう選手が非常に多いことだ。現在のサッカーではどのポジションの選手も運動量を求められているから、選手たちは走りやすい「固定式スタッド」のシューズを選びがちで、芝生をしっかりつかむ「取り替え式スタッド」のシューズは避けられる傾向がある。
しかし滑って転び、大事なチャンスを逃したり、あるいはあっさりと相手に得点を許しているようでは、水まきが悪いのか、それともシューズ選びが問題なのか、外から見ている者としては、なんとも理解し難いものがあるのである。
■繊細なグアルディオラ監督の流儀
試合前やピッチにまく水の適切な量を決めるのは、そう簡単な話ではないらしい。クライフのまな弟子と言っていいペップ・グアルディオラが監督を務めていた時代のバルセロナ(2008年~2012年)では、ハーフタイムのロッカールームにグラウンドキーパーがはいってくることが珍しくなかった。彼は分単位のスタジアム周辺の天気予報のデータをキャプテンやコーチに見せ、後半に向けどのくらい水をまいたらいいか、要望を聞いていたという。
日本のスタジアムでは、ボールが転がるたびに水を巻き上げている光景(明らかに水のまき過ぎだ)や、散水した水の小さな粒が芝生の表面について、まるで霜が降りたかのように芝面が白く見えるところがある。そうした「霜降りピッチ」では、試合が始まってからしばらくは選手の足跡が見えたり、ボールが転がった軌跡がまるで絵を描いたように見える。かつての国立競技場がそうだった。
散水方法や風向きによって、スタンド前列の観客が「被害」をこうむることも少なくない。夏なら冷却効果があって好ましいかもしれないが、2月や12月などの寒い時期に予期せぬ(シーズンチケットホルダーなら先刻承知か)「雨」にずぶぬれになったら悲惨だ。埼スタでは、散水が始まる前、タッチラインの中央、ピッチのすぐ外のグラウンドレベルに置かれたテレビカメラには、しっかりとビニールのカバーがかけられる。
天気の良い日の午後の「水芸」には、その幻想的な光景とともに、ひそかな期待がある。「虹」である。メインスタンドに座っていると、背後からの太陽がピッチのバックスタンド側の半分、日差しがまだ当たっているあたりの「水柱」に当たる。すると当然、虹が出るのである。
舞台でお姉さんたちがやる「本家水芸」をサッカースタジアムの「水芸」が超えるのは、まさにこのときなのである。