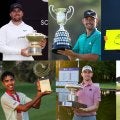王者の源流~大阪桐蔭「衝撃の甲子園デビュー」の軌跡第6回 大阪桐蔭吹奏楽部の公式ホームページによると、2005年に野球部…
王者の源流~大阪桐蔭「衝撃の甲子園デビュー」の軌跡
第6回
大阪桐蔭吹奏楽部の公式ホームページによると、2005年に野球部の応援を目的として部が誕生したと記してある。現在では甲子園で披露する圧倒的な"美爆音"のみならず、全日本吹奏楽コンクールの「金賞」をはじめ、世界大会でも実績を残し、各地での演奏会や数々のテレビ番組に出演するなど、日本屈指のブラスバンドとして知られている。
吹奏楽部の起源も、じつは1991年にあった。
野球部が1990年の近畿大会でベスト4まで進出し、初の甲子園となるセンバツ出場を決めると、部長の森岡正晃は応援の青写真を描いた。
「PLの曲を入れたい」
面識のある母校のブラスバンド担当の教師に、PL学園の『ウイニング』や『ヴィクトリー』など、甲子園ファンには馴染み深い楽曲の継承を願い出ると、こう返答された。
「森岡くんの気持ちはわかるが、譜面を渡すわけにはいかん。これはPLの『誇り』や」
野球部がそうであるように、ブラスバンドもゼロから築き上げたPL学園の魂であることは、森岡も知っている。だからこそ、それ以上は食い下がらなかったが、その教師から大きなヒントをもらえた。
「映画の『ベン・ハー』を観なさい。そこにすべてが詰まっている」
日本では1960年に公開され、アカデミー賞を総なめにした歴史超大作を、森岡は「観る」以上に「聴いた」。頭のなかで『ベン・ハー』と甲子園をシンクロさせ「チャンスではこの音楽を」といったシミュレーションを重ね、イメージを大阪桐蔭の音楽教師に伝えた。そして、母体である大阪産大の吹奏楽部とともに、オリジナルのチャンステーマをつくり上げた。
甲子園では四条畷学園がブラスバンドの応援部隊として演奏を担当した。腹の底まで響き渡る重低音。大太鼓とスタンドのかけ声も相手を威圧する。楽曲と同時に頼み込み、こちらは使用許可をもらったPL学園直伝の人文字がアルプススタンドで躍る。
センバツで応援部隊を統率していたのが、3年生の今宗憲(こん・むねのり)だった。
高校野球では2年生が応援団長を務めることが多いのだが、この時は今がその役を担っていた。本来ならセンバツは下級生に任せるべきだったが、初めての甲子園であったことから、「俺たちにも何かできることはないか」と考えた。大太鼓の田中雄一郎、60キロもある応援旗を持つ松村俊輝ら、背番号をもらえなかった3年生と話し合い、それぞれ役割を買って出た。
森岡が目を細めながら言う。
「応援団長の今だったり、(ベンチ)メンバー外の子たちが『自分がやります』と、こちらが言わなくても率先して裏方の仕事を買って出てくれた。それも、あの年の大阪桐蔭の強さやったと思います」
今でこそ、ベンチ外メンバーもレギュラーと同等にクローズアップされるようになったが、30年前の高校野球での彼らの立ち位置は、あくまで補欠だった。
大阪桐蔭のメンバーとして力になりたい──その使命感が今を突き動かしたのは事実だ。しかし、冷静な自分も否定はできなかった。
「桐蔭が甲子園に出たことはホンマにうれしかったし、応援も楽しみましたけど、心のどこかで『恥ずかしい』っていう思いがありました。野球部なのに応援団って......親にも堂々を話せませんでした。だから、夏は『応援団長はもうええかな』って思っていました」
夏の大阪大会は従来どおり、2年生部員が応援団長を務めていたこともあり、今はセンバツの経験や応援の手順を教える腹積りでいた。ところが...。
「おまえがやれや。今がやらんかったら、アルプスが盛り上がらん」
主将・玉山雅一からの突然の説得だった。
「あんな惨めな思いは、もうええわ」
今はそう返したが、玉山も引かなかった。
「ダメや! おまえがやらんと、応援団が締まらんし、野球部もまとまらん」
玉山が今にこだわった理由を明かす。
「『センバツで応援団長をやったから』ってわけやないんです。言葉はおかしいかもわからんけど、今は"メンバー外のキャプテン"みたいな立場やったんです。人柄はええし、まとめる力もあった。3年生が30人おったなかでメンバー外の選手は当然出てくるわけで、今はそういった子たちの気持ちをよう理解してたんです。ベンチ入りメンバーとの間をうまく取り持って、チームに摩擦が生じないようしてくれたんです」
夏の甲子園でも応援団長を引き受けた理由を、今は「主将の存在」とはっきり言った。
「僕らみたいな部員にも目を配れるのが、玉山というキャプテンなんです。何気ないやり取りでしたけど、あの言葉がなかったら、絶対に応援団長をやっていなかったです」
夏の甲子園開幕直前に主催の朝日新聞で掲載された『代表校の戦力評』によると、総合「A」は、センバツで大阪桐蔭を下した準優勝校の松商学園、同ベスト8の鹿児島実、前年夏の優勝校の天理、そして大阪桐蔭と、49代表のうちわずか4校だった。
前評判の高さに加え、ベンチとアルプスの結束を固めた大阪桐蔭は、大会7日目の2回戦からの登場となった。相手は同じく初出場の群馬・樹徳高校だった。
初回に1点を先制されながらもその裏、一死二、三塁とすかさずチャンスをつくる。アルプススタンドからの重低音を背に打席に立った4番の萩原誠が、樹徳の先発・戸部浩の内角寄りストレートを狙いすましたかのようにレフトに弾き返し、すかさず逆転。大阪桐蔭は3回に2点、4回に3点、5回にも2点を追加するなど樹徳を圧倒した。
「悔しい気持ちがあるのにチームを支えてくれている。あいつらのためにも頑張らないと......」
メンバー外の選手への思いを抱き打席に立っていたという萩原は「天性の長距離砲」と言われる一方で、じつは研究熱心な選手だった。現在ほど情報がなかった時代とはいえ、対戦相手の映像を仕入れるなど、最低限の対策は講じていた。「対戦相手のビデオは......見てたかな?」と曖昧に振り返る選手が多いなか、萩原は「見ていました」とはっきり口にした。
「どんなタイプのピッチャーかを確認するくらいでしたけど。真っすぐで攻めてくるのか、インコースが多いのか......とか。僕は警戒されていたので、どういう攻め方になるのかなとイメージしながら見ていましたね」
さらにこの夏は、「大会屈指のスラッガー」としても闘志を燃やしていた。
「萩原くんに僕の記録を抜いてほしい」
大会直前、森岡がPL学園OBから伝えられたのは、西武の主力として活躍していた清原和博の言葉だった。1985年夏の甲子園で「1大会5本塁打」の記録を打ち立てた(当時)スーパースターからの激励は、萩原にとってこれ以上ないモチベーションになった。

1991年夏、初戦の樹徳戦で本塁打を含む4安打2打点の活躍を見せた元谷哲也
そして萩原は、結果で示した。
樹徳戦の6回、2番手左腕の橋爪保の内角からシュート回転し真ん中に甘く入ったストレートを強振すると、萩原自身も「手応えがあった」という打球はレフトが数歩動いただけであきらめるほどの完璧な一発だった。
3打数2安打(1本塁打)4打点。萩原が与えたインパクトは十分だった。その主砲よりも結果を残したのが5打数4安打(1本塁打)2打点の元谷哲也だった。だが、チームの誰よりも打ったにもかかわらず、主役の座を萩原に持っていかれる形となった。
「あいつ(萩原)が打ったら、いくらほかの選手が活躍してもかすんでしまう。でも、個人的にはホームランもそうですし、樹徳戦はイメージどおりのバッティングができました」
この結果は、元谷の意地の表れでもあった。
大阪大会では不振の澤村通に代わり1番を打つことが多く、井上大、萩原に次ぐチーム3位の打率.385を残すなど、調子がよかった。甲子園でもそうだと思っていたが、試合前に「定位置」の2番と言われ、監督の長澤和雄に抗議している。
「大阪大会では1番を打って結果も出してきたのに、なんで2番やねん!」
そう憤る元谷が冷静さを取り戻せたのは、森岡からこう諭されたからだという。
「監督にも考えがあってのことなんやし、納得せぇ。甲子園ではチームのためにつなぐだけじゃなしに、自分を生かすためにつなぐことも、おまえならできると思っている」
1番が出て、自分が送り、井上、萩原でランナーを還す──大阪桐蔭の"お家芸"を元谷はあらためて肝に銘じた。
「スタメン9人が4番バッターである必要はないんでね。僕は送りバントも得意やったし、甲子園ではつなぎに徹しました。樹徳戦の次から調子が落ち気味になってきたし、結果的によかったかもしれません」
自らがつなぎ役に徹することで打線は円滑に機能し、大阪桐蔭は15安打11得点を奪い快勝した。
そしてベスト8をかけた次の相手は、初戦でサヨナラ勝ちと勢いに乗る秋田に決まった。
「秋田? 勝てるやろ」
ミーティングも早々に切り上げ、大阪桐蔭ナインは心身の休息に励んだ。次戦で壮絶な戦いが待っているとは、この時、知るよしもなかった。
(つづく)