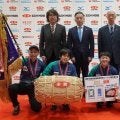第2セットを奪い返し、第3セットに向かうセット間のことである。 相手がトイレットブレークでコートを離れたその間、大…
第2セットを奪い返し、第3セットに向かうセット間のことである。
相手がトイレットブレークでコートを離れたその間、大坂なおみはコーチのウィム・フィセッテを呼び、通常より長めの「コーチング」を受けた。

オーストラリアのファンの大声援に応える大坂なおみ
「どうした?」
ベンチに駆け寄ったコーチは、まずはそう声をかけて、大坂から話を引き出す。
「なんか固くなってしまう」「ストレスを感じちゃう」
第2セットを取ってもなお不安そうな大坂に、コーチは、穏やかな口調で話しかけた。
「でもこの2試合、リラックスしている時には『本物のなおみ』になっていたよ。すべては君次第だ。スコアを気にせず、ポイントごとにベストを尽くそう。そうすれば打ち合いを支配できる。ミスをしてもいい。ミスはテニスの一部なんだから」
その言葉をひとしきり聞き終えると、今度は「サーブはどうすればいいと思う?」と尋ねる。その問いにも、コーチは即座に応答した。
「もっと球種を混ぜていくべきだ。とくにボディ(相手の身体の正面を狙うサーブ)を使ったほうがいい。同時にサーブの質、そのものを上げていこう。
何度か時速120キロ台のセカンドサーブがあったが、あれは君らしくない。ただ、それほど気に病むことはないよ。もう少しバリエーションを増やしていけば大丈夫だ。まだ今季2試合目だよ。ポイントを重ねるごとに調子を上げていけばいいさ」
これらの助言が、功を奏しただろうか。「試合中にコーチに言われたことは、いつも忘れちゃうの」と困ったように白状する大坂だが、この時のコーチの言葉は、ちゃんと覚えていたようだ。
「リターンで攻撃的にいくように言われた。そのとおりにできたと思う。あとはセカンドサーブで、球種を混ぜていくようにと」
サーブからの主導権掌握、そして、リターンでのポイント獲得率の上昇——。
それら、初戦の辛勝から持ち帰った「継続すべき点」と「改善できる点」のいずれにも、2回戦の大坂はひとつの解を示してみせた。
同会場で行なわれたATPカップの予選リーグが終了したため、2回戦にして初めて大坂を迎えたセンターコートは、ほぼ満席のファンで埋め尽くされていた。世界4位の大坂が対戦するのは、14位のソフィア・ケニン(アメリカ)。昨年大躍進を果たした1歳年少のロシア系アメリカ人は、大坂が10代の頃から「私より歳下で、でも常に私よりも強い子」として認識していた少女だったという。
そのケニンを「ライバル」と呼ばれることに小さな拒絶感を示した大坂だが、「重要な局面でとても固くなった」その訳は、「強い子」への意識が影響したかもしれない。第1セットは終始優勢に進めるも、ブレークチャンスやタイブレーク終盤でミスが重なり、大坂が第1セットを失った。
「よくなかった点を修正しなくては」
自らにそう言い聞かせた第2セットで、大坂に見られた明確な変化が、初戦後に「改善点」として挙げたリターンである。
第1セットは駆け引きにとらわれて消極的になっていたが、2セット目以降は「躊躇せず、思いっきり打っていかなくては」と心を決める。さらにはリターンで崩したあと、すぐにストレートや逆クロスに展開し、次々にウイナーを奪っていった。
そうして第2セットを奪ったあと、冒頭で触れた、コーチに助言を求める場面が訪れる。
その数分間の会話を経て、第3セットは6−1で奪い去った。リターンでのポイント獲得率は、第1セットの31%から、第2セットは55%に上昇。さらに第3セットでは、61%に達していた。
センターコートに詰めかけた老若男女入り交じるファンは、昨年の全豪オープン女王の勝利を、万雷の拍手と歓声で祝福する。その優しい音を浴びながら、大坂は「初めて来た時から、オーストラリアのファンはいつも親切だった。去年の全豪では、『オージー、オージー、オージー!』のコールで応援してくれたし」と満面の笑みで応じた。
オンコートインタビューを終えた時には、客席から「オージー」コールが起きる。その声援につなぎ止められたかのように、大坂はたっぷりと時間をかけて、ファンのサインの求めに応じ続けた。
ボールにサインをもらった少女が、興奮の面持ちで父親に報告する。テニス少年たちは、身につけていたシューズやリストバンドにサインを求めた。「タオルをちょうだい!」と訴える少女には、一度しまったタオルをバッグから取り出し、サインを入れて手渡しする。そのたびにテニスコートの一角には、幸福な空間が広がっていった。
試合を重ねるごとにプレーの質を上げる大坂は、そのたびにファンの声援も獲得していく。
その声を追い風に、さらに加速を強めていく。









![20歳ティエン、世界12位を圧倒しグランドスラム初の8強!2015年キリオス以来の最年少準々決勝進出者に[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012520260204138600.jpg)




![アルカラス、難敵ポールを退け3年連続の8強進出!史上最年少の生涯グランドスラムに邁進[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012516260245513700.jpg)