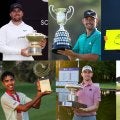「やっぱり、国旗のついたユニフォームを着るとテンション上がりますよ!」と、日比野菜緒は笑顔で言う。 今年2月に行なわ…
「やっぱり、国旗のついたユニフォームを着るとテンション上がりますよ!」と、日比野菜緒は笑顔で言う。
今年2月に行なわれたフェドカップ(女子国別対抗戦)は、彼女にとって、通算3度目の代表選出だった。

「フェドカップ優勝」を目標のひとつに掲げる日比野菜緒
シングルスの2番手として日の丸を背負い、戦績は1勝1敗。価値ある白星をひとつもたらしたことと、自分のテニスの方向性が見えた充実感。同時に、チームを勝利に導く2勝目を、接戦の末に掴みそこねたことへの悔い……。それら複数の情動が、代表ジャージに編み込まれた。
日比野が抱く代表への想いの原点には、同期選手たちへのコンプレックスに似たライバル心と、オーストラリア留学がある。
今でこそ同期のなかでも出世頭の日比野だが、小・中学生時代はけっしてエリート街道を歩んできたわけではない。
ジュニアの強化選手に選ばれるのは、国内タイトルを総ナメにしていた尾崎里紗や、全豪オープンJr.ダブルスで準優勝した穂積絵莉と加藤未唯――それら同期の強化選手とは、同じ遠征先に出かけても、「ナショナル選手とそれ以外は、間にきっちり線を引かれている」と感じていた。
ならば、自分は独自の道を進むとばかりに、高校時代はオーストラリアへ留学する。そのホームステイ先の家族が、いかなる競技でも国際試合となればテレビの前に集い、オーストラリア代表を応援する姿に新鮮な感動を覚えた。
「こんなふうに誰かに応援してもらえる、勝てばみんなに喜んでもらえるのが、国際試合なんだ」
スポーツを愛するホストファミリーの情熱は、日本を離れたからこそ感じていた郷愁とも重なり、彼女のなかで代表への憧憬としてかたどられた。
日比野が念願のフェドカップ日本代表に選出されたのは、前年末にツアー初優勝し、ランキングトップ100入りした2016年のこと。ただし、代表への強い思い入れは、歓喜と失意が表裏となり、不安定に回転するコインのようなものでもある。
「初めて選ばれた時は、緊張感から、試合の前も後も泣いていて……」と、日比野は当時を回想する。
2度目の選出は、昨年2月にインドで行なわれたアジア/オセアニアゾーン予選。その時は「いろんなことにイライラして、わけもなく周囲に当たり散らした」。それでも、通算3勝1敗の戦果をあげてチームの勝利に貢献するが、そのわずか3~4週間後には、ワールドグループ復帰をかけた4月の対イギリス戦から外れる旨(むね)が告げられる。
「あれは、落ち込んだな……。わかってはいたけれど、悔しかったですね」
インドでの1週間に及ぶアジア/オセアニアゾーン予選を戦い抜いたメンバーから、外れたのは自分だけだった。代わりに選出されたのは、BNPパリバ・オープンで優勝し、大躍進を果たしたばかりの大坂なおみである。
その戦績だけを見れば、この結果はある程度は予見できていた。それでも、胸をふさぐネガティブな感情は、打ち消しようがない。練習コートに行きたくない、テニスもしたくない、やめてしまいたい……。そんな捨て鉢(ばち)な衝動にも襲われたという。
それらフェドカップに端を発する煩悶(はんもん)を、洗い流してくれたのもまた、フェドカップだった。
日本対イギリス戦が行なわれたのは、日比野が日頃から練習拠点とする兵庫県三木市のブルボンビーンズドーム。見に行くつもりはなかったものの、コーチに説得されて渋々会場に足を運んだ日比野の目に映ったのは、チームの勝利のために必死に戦う盟友たちの姿だった。
「あれだけがんばっているみんなの姿を見たら、私が外されたことなんて、どうでもいいかって。日本も勝ったし、また選ばれるようにがんばろうって思えて」
日本が勝利を決めた時は、選手やスタッフたちに手招きされ、歓喜に沸くチームの輪に加わる。大坂に「出てくれてありがとう」と言った時、わだかまりはスッと消えた。
日比野にとって初の日本開催となった今年2月のフェドカップは、過去2度の代表選出時に比べ、もっともいい心身の状態で迎えられた戦いだったという。テニスそのものに目を向けても、現在はスライスやネットプレーを取り入れて、プレーの幅を大きく広げている最中。精神面でも、「いつでも自分のいいプレーができる」心理状態を、徐々に体得しつつある。
そんな彼女が今、目指すのは、「グランドスラムでのベスト8以上」。そしてもうひとつが、「フェドカップで優勝」することだ。
「日本のテニス界に恩返しするなら、フェドカップなのかなと。現役中に優勝できなかったとしても、監督やコーチとして、いつか何らかの形で……」
国旗のついたユニフォームを身にまとった時、自ずと覚える高揚感――。その胸の高鳴りが、彼女を今へと導いて、この先へと歩を進ませる。













![40歳ワウリンカ、逆転で5年ぶり全豪白星。主催者推薦で見せた“最後の挑戦”[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012008260622393600.jpg)
![ジョコビッチ、全豪通算100勝達成!メルボルンで刻んだ新たな節目「歴史を作ることが大きなモチベーション」[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/raw/2026012008260189385600.jpg?bg-color=000000&crop=546%2C546%2Cx91%2Cy0&width=120&height=120)
![世界20位のポール、8か月ぶりの「完全な健康」で全豪白星発進「今年の第一目標は、痛みなくプレーすること」[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012007260526688600.jpg)