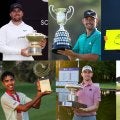『前へ』。 時代は変われど、故・北島忠治元監督の信条だった「前へ」の精神は生きている。苦境に陥ってもひるまず前へ。関東…
『前へ』。
時代は変われど、故・北島忠治元監督の信条だった「前へ」の精神は生きている。苦境に陥ってもひるまず前へ。関東対抗戦の4位扱いとなった明治大学が大学選手権決勝で天理大学を22-17のスコアで破り、22年ぶりの優勝を飾った。

22年ぶりの優勝を抱き合って喜ぶ明大フィフティーン
東京都内に初雪が観測された1月12日の東京・秩父宮ラグビー場だった。ラスト5分、リードは5点。明大は猛烈な天理大の反撃を浴びた。それでも、しぶとく前に出るタックルでしのぐ。チームの結束と信頼は崩れない。
ラスト1分、明大陣の中盤で天理大ボールのスクラムになった。直前、明大はフロントロー陣を3人そろって交代させた。先発HO(フッカー)武井日向(3年)が交代のHO松岡賢太(3年)にこう、言葉をかけたそうだ。
「ヒットで前に出ろ!」
ラストワンプレー。両チームの意地とプライドがぶつかる。紫紺の明大と黒の天理大の塊がドンとぶつかる。スクラムが崩れた。終了のホーンが鳴る。2度目の組み直しだ。
2万人を超える大観衆で埋まったスタンドがどよめく。ホイッスルが鳴るまでの残りワンプレー。3度目、紫紺のジャージの塊が当たり勝つ。崩れそうになりながらも前に出た。押し込もうとしていた黒色ジャージの天理大だが、ナンバー8のファウルア・マキシ(4年)がたまらず、右に持ち出した。
明大ナンバー8の坂和樹(3年)がマキシをつぶす。天理大の連続攻撃にタックル、またタックル。最後、天理大の切り札のCTB(センター)シオサイア・フィフィタ(2年)にパスがつながろうとした瞬間、明大のCTB森勇登(2年)が鋭い出足で前に出る。ノックオン。
歓喜の爆発。「メイジ! メイジ!」。紫紺の小旗が揺れる観客席からの大歓声に包まれ、主将のSH(スクラムハーフ)福田健太(4年)は泣いていた。試合後、勝因を聞かれると、こう声を張り上げた。
「メイジのプライドを持って戦えたことがすべてだと思います」
メイジのプライドとは?
「紫紺のジャージを着た以上は勝たないといけない。ディフェンスでもアタックでも前に出続ける。すべてのところで押す。ラグビーに対する姿勢でも。それがプライド」
表彰式が終わると、明大フィフティーンはピッチわきで待つ、試合に出場しなかった”ノンメンバー”のところに猛ダッシュで駆け出し、ひとつの輪となった。チームとしての一体感、これぞ学生ラグビー、いやチームスポーツの美徳のひとつである。
活躍した4年生のWTB(ウイング)高橋汰地(たいち)がしみじみと漏らした。
「みんなが泣いてくれていたので、自分も泣いちゃいました。こいつらと一緒にラグビーやってよかったなあって」
この日、宿舎での試合前ミーティングでは、ノンメンバーによるビデオメッセージが流された。熱い檄(げき)が続いた。
「日本一のBチームがいつも練習相手しているんだから、おまえたちは日本一だ!」
「メイジのスクラムは日本一だから、天理を圧倒してこい!」
試合直前のロッカー室では、田中澄憲(きよのり)監督が「誇り」を訴えた。こう言葉をつけ足す。
「メンバー外のメンバーが見ても、勝ち負けを意識することなく、誇りに思えるようなプレーをしようと話しました」
決勝戦のゲームテーマは、今季のチームスローガンの『Exceed』だった。昨季の決勝では1点差で帝京大に惜敗した。その悔しさを乗り越える、昨季のチームと自分を超える、結果を上回る、すなわち優勝である。
決勝の相手は王者・帝京大を破って勢いに乗る天理大だった。昨年春、夏の練習試合では敗れている相手でもある。突破役が、トンガ出身の3選手だったが、高橋はこう説明した。
「3人は脅威だったんですが、そこばかりを意識すると他の選手に走られてしまうので、メイジはいつも通りのディフェンスをして、前に出るディフェンスを意識しました」
メイジのディフェンスとは、前に出る時はしっかり出て、出ない時は周りとのコネクション(連携)を守ることである。キーワードが「2in Fight」と「BIG」。前者はふたりで倒しに行くダブルタックル、後者は「Back In the Game」の略で、タックルなどで倒れたら2秒以内にディフェンスラインに戻ることを意味している。これが、しぶといディフェンスにつながった。
福田主将は言った。
「とくにディフェンスで成長していると感じました。コミュニケーションの部分とか、タックルした人間がすぐに立って次の仕事を探すこととか、すごくできたと思います」
勝負のアヤでいえば、前半終了間際の天理大の猛攻をゴールライン際で防ぎ切ったのは大きい。最後、天理大のLO(ロック)アシペリ・モアラ(1年)がインゴールに飛び込んだ際、明大フォワードが束になって食い止め、ボールをグラウンディングさせなかった。メイジの執念だった。
加えて、勝因はボール争奪戦、ブレイクダウンでの奮闘だった。みんな、からだを張った。相手のボールを奪取するターンオーバーが6回。
これは明大のフィジカルアップゆえだろう。1年間のS&C(ストレングス&コンディショニング)のテーマが「外国人に負けないからだ作り」だった。各自、目標値を設定し、科学的な筋力トレーニングに励んできた。さらにいえば、レスリングコーチの指導も受けて、効果的なからだの使い方も磨いてきた。人に対するタックル、ボールに対する絡み、低さ、相手の下をとる技術…。
接点でも「前へ」である。フッカーの武井は言った。
「ディフェンスでも、アタックでも、1センチでも前に出る。倒れても、すぐ立ち上がって、1センチ前に出ることを意識していました。その1センチでサポートの入り方、バックスの勢いが変わってくるので」
ディフェンスが固まれば、アタックにもリズムが生まれる。事前の分析、周到な準備も奏功した。天理が「外から内の方向転換にもろい」と読むと、アングルチェンジで何度もゲインした。前半の中盤の高橋のサインプレーのトライもそうだった。サインが「タンク・エックス(単9X)」。
ラインアウトから紫紺のジャージの9番の福田がボールを持ち出して、左に走った。そこに、「X」のごとく、交差するようにWTB高橋が駆け込んだ。高橋はそのままタテに切れ込み、中央に飛び込んだ。ゴールも決まり、12-5とリードした。
高橋が痛快そうに笑う。
「狙い通りでした。(走り抜けて)気持ちよかったです」
勝負の最大のポイントだったスクラムでは、明大は持ち前の「修正力」を見せた。天理大の低くて強固な押しに苦労し、序盤は相手ボールのスクラムでコラプシング(故意に崩す行為)の反則を相次いでとられた。武井によると、フロントロー陣が食い込まれてはじき出されていたためだが、すぐに連携をとり、ヒット勝負に出て後ろ5人の押しをもらうこと、相手の首を抑えて低く沈むことを確認し合ったそうだ。
武井がこう振り返る。
「横のまとまり、結束も意識しました。そしてスクラムも前へ、です」
今季のシーズンを振り返ると、チーム作りのカギは対抗戦で慶応大学、早稲田大学に敗れた後にあっただろう。対抗戦4位扱いとなり、大学選手権ではノーシードとされた。選手が自信を無くしてもおかしくなかった。
だが、大学選手権前、田中監督はミーティングで故・北島忠治元監督の写真を部員たちに見せたという。
「この人を誰か知っているか?」
当然、みんな知っていた。「有名な言葉は何だ?」と聞いた。
ラグビー部の寮の食堂には「前へ」との言葉が掲げられている。田中監督が思い出す。
「”前へ”という言葉は知っていたので、それはどういうことだと思うと聞いたんです。僕は前へというのはプレースタイルというより、生き方というか、哲学みたいなものだと思うと説明しました。4位という状況だけど、そこから逃げないで進んでいくという話をしたんです」
そのコトバ通り、「前へ」とは、どんな状況でも前に出る。苦境にあっても、自分で道を切り開く。新しい時代を創り出す気概を言うのであろう。
また、田中監督の勧めで、4年生22人全員でラグビー寮がある八幡山駅近くの中華料理店で「決起集会」を開き、その後、スーパー銭湯に行った。食事をしながら、とことん話し合って、チームの方向性を確認した。
高橋が「4年生の熱量」を強調する。
「全員が本音でした。感極まって泣いている人もいた。全員がひとつになりました」
いろんな要因がかみ合っての名門復活である。田中監督の3年時に大学日本一になって以降、明大は長い低迷期に入っていた。1996年に北島前監督が亡くなった後はチームの指導方針もぶれ、好素材をうまく育成できなくなった。危機感を抱いた明大はラグビー部の立て直しに乗り出した。
とくに2013年に監督に就任したOBの丹羽政彦さんは単身でラグビー寮に住み込み、私生活からの改善に乗り出した。チーム作りに大事な「規律」である。いまや、古い慣習は消え、掃除も洗濯も全員でやる。理不尽な上下関係は消えた。新たなクラブ文化が芽生え始めた。
そして、昨季、トップリーグのサントリーに在籍していた田中監督がHC(ヘッドコーチ)に就いた。昨季は練習のマインドセット(心構え)をたたき込んで、今季はサントリー時代、エディー・ジョーンズ前日本代表HCからも学んだ試合分析やシステムなど、勝つためのノウハウをチームに落とし込んできた。
例えば、明大の練習は授業前、朝6時半からスタートする時もある。選手は5時頃には起きて準備しないといけない。田中監督が述懐する。
「寝ぐせをつけたままの学生がいたので、”僕が寝ぐせをつけてきたらどうする”と聞いた。”やる気がないと思います”と返ってきた。”お前も同じことをしているんだ”って」
今季は寝ぐせをつけている学生は皆無となった。チームは変わったのだ。
1年前の1点差負けの決勝と比べ、チームとして変わった点を聞けば、田中監督はこう言った。
「去年は決勝戦まで行って満足したチームだったと思います。でも、今年は本気で日本一を獲りにいかないといけないという自信を選手が持っていました」
言葉に実感がこもる。
「ほんと、負けから学んで成長したチームだと思います。タフになった。部員126名の努力とハードワークの結果が最後に最高の形で表れて非常にうれしいです」
22年ぶりのV。だが田中監督は少し笑って、こうつづけた。
「あまり実感がなくて、初優勝のような気持ちです」
確かに時代とともにプレースタイルは「重戦車」から展開力を加えたバランスのいいチームに変わった。でも「前へ」の精神は不変だ。たくましく生まれ変わった明大が新たな時代を創り出す。