「失礼じゃなかったかなあ……」 シトシトと雨が降り注ぐ6月初旬のある日。「きっと面白い話が聞…
「失礼じゃなかったかなあ……」
シトシトと雨が降り注ぐ6月初旬のある日。「きっと面白い話が聞けるはず」という期待と、一抹の不安を感じながら、とある自動車販売店の一角に座っていた。
今回、話を伺うのは甲子園に出場した元球児。しかしながら、主題になるのは華々しい活躍ではなく、彼がある試合で犯した”ミス”の話だ。事前の電話では、快く取材を引き受けてくれたように思えたが、実際の対面を前に、小心者の筆者は幾ばくかの罪悪感に苛(さいな)まれていた。
「ギリギリになって申し訳ございません! 今日はよろしくお願いいたします」
到着と同時に、ハキハキとした口調であいさつを述べる青年。短く整えられた頭髪、ビシッとスーツを着こなす姿は、”デキる営業マン”そのものだ。

勝利まであと1アウトから逆転負けを喫した開星ナイン
彼の名は、本田紘章(ひろあき)。2年春、3年春夏の計3度甲子園に出場しているが、名前だけではピンとこない人が多いかもしれない。しかし、こう言えばすぐわかるのではないだろうか。「開星のセンター」と――。
高校野球では、時に好プレー以上に観衆の脳裏に深く刻まれるミスが生じることがある。1979年夏の星稜(石川)×箕島(和歌山)戦で、星稜の一塁手・加藤直樹が転倒し、ファウルフライを捕球し損ねたシーンや、1998年夏に延長15回の熱戦に終止符を打った宇部商・藤田修平の「悲運のサヨナラボーク」は、その代表例だ。
ここ10年で”一番”と言っても過言ではないミスが、2010年夏の仙台育英(宮城)と開星(島根)の一戦で生まれた。
開星の2点リードで迎えた9回表。1点差に詰め寄られ、なおも二死満塁と攻め込まれる。続く2番打者は、初球を打ち上げ、打球はセンター方向へ。勝利を確信した開星の2年生エース・白根尚貴(DeNA)は、安堵の表情を浮かべながらガッツポーズを見せる。誰もが開星の勝利を確信したその瞬間、センターを守っていた本田のグラブから打球がこぼれ落ち、二者が生還。これが決勝点となり、開星は痛恨の逆転負けを喫したのだ。
勝利直前に起こった”まさか”の落球。その鮮烈さから、いつしか彼は「開星のセンター」と呼ばれるようになり、甲子園でフライの落球が起きた際には「開星のセンターを思い出した」などとインターネット上で書かれることも少なくない。
毎年夏が近づくと、「高校野球名勝負」のひとつとしてこの試合が紹介されることも多く、そういった番組を目にするたびに、彼が今どうしているのか、あのプレーが彼の人生にどういった影響を与えたのか……。何とか話を聞きたいと思っていた。
取材開始と同時に、「古傷をえぐるようなことを……」と謝意を述べると、笑顔で「いえいえ、大丈夫ですよ。それに、センバツのことに触れてもらえることは今までなかったので、ありがたいです」と答えてくれた。
この「センバツのこと」とは、本田にとって初めての甲子園出場となった2年春(2009年)のセンバツでの活躍を指す。
開星にとって初めてのセンバツ出場となったこの大会。初戦の相手は、前年の明治神宮大会優勝の慶応義塾(神奈川)。「大会屈指の本格派右腕」と呼ばれていたエース・白村明弘(日本ハム)を擁し、優勝候補の一角に挙げられていた。
この試合で、背番号15ながらスタメンに抜擢された本田は、白村から決勝タイムリーを放つ活躍を見せたのだ。
「打者有利のカウントで、『思いきりいこう』と思えたのがよかった。いま振り返っても、あの打球が高校では一番いい当たりだったと思います」
試合後には、”活躍選手”としてインタビューも受けた。初めての甲子園で見事に結果を残した本田だが、本人曰く、中学までは目立った選手ではなかったという。
「小学校、中学校のときはバッテイングが全然ダメで、足と守備で何とか……という感じでした。実は小学校で野球に区切りをつけて、中学では陸上部に入ろうかなとも考えていたんです」
地元の強豪チームとして名高い「乃木ライオンズ」で野球を始め、中学時代も同チームの中等部にあたる軟式クラブ「乃木ライオンズシニア」でプレー。開星時代の後輩・白根は、小学校時代から同じチームの所属で、「同学年みたいに接してくるヤツでした(笑)」と振り返る間柄だ。
中学時代の先輩の多くが主力として活躍していたこともあり、本田も自然な流れで開星に進学。入学後、同校の”名物”ともいえるウエイトトレーニングに取り組んだことで、大きな進化を遂げる。
「ウエイトで体ができてくるにつれて、打球が変わっていきました。特に1年の冬からセンバツにかけては、自分でも『レベルが二段階くらい上がった』と感じたぐらいで」
今までは快心のスイングでもフェンスに届かなかった打球が、軽々とフェンスを越えていく。打撃練習で放つ打球に自分自身も驚いた。
チームが4強入りした1年秋の中国大会ではベンチ外だったが、冬場の成長を評価され、センバツで公式戦初となるメンバー入りを果たす。大会直前の好調を買われ、センバツの2試合にスタメン出場した。
2年秋からは不動のレギュラーとなり、主に「3番・センター」で出場。チームは秋の島根大会、中国大会を立て続けに制覇し、翌2010年のセンバツ出場を決めた。
当時の開星は、エース・白根、1番を打つ糸原健斗(阪神)の投打の柱だけでなく、脇を固める選手にも力があり、「優勝候補の一角」との声も少なくなかった。しかしながら、センバツでは21世紀枠出場の向陽(和歌山)の前に初戦敗退。野々村直通監督が「末代までの恥」と発言したことが波紋を呼んだ試合だ。
センバツ終了後には、監督交代を余儀なくされる。「お前ら、野球辞めちまえ!」と罵声を浴びせる人物がグラウンドに表れ、満足に練習できない時期もあったが、高いチーム力は揺るがなかった。
「自分たちの不甲斐なさで監督に迷惑をかけてしまった……と落ち込んでいましたが、下を向いていても仕方がない。とにかく、やれることをひとつでも多くやろうと切り替えて練習していました」
監督交代騒動の直後に行なわれた春の島根大会は4強止まりだったものの、春夏連続出場がかかった夏は見事優勝。5試合を戦い、失点はわずかに1。バックも無失策で守り抜いた。
同校史上初となる春夏連続出場を果たし、「今度こそ甲子園で勝つ」と意気込んで臨んだ仙台育英との初戦は、互いに得点を奪い合うシーソーゲームとなる。
3-3の同点で迎えた7回裏。この回先頭の5番・白根がレフトにソロ本塁打、さらに8番打者がスクイズを決め、勝ち越しに成功する。
2点リードで迎えた9回表、白根はテンポよく二死を奪うが、そこから安打と死球でピンチを招く。その直後の痛烈な打球をショートが弾き、1点差。続く1番打者の安打で二死満塁となり、2番打者が初球を打ち上げる。本田も素早く落下点に入り、勝負は決したかに思われた。
「打球が飛んできているのに、『これを捕ったら終わり。捕ったあとは、整列して、アルプスにあいさつ、ベンチを片付けて……。それから宿舎で何をしようかな』と、終わったあとのことばかり考えていました。目の前のプレーに集中できていなかった」
上空に舞っていた風に押し戻され、目測よりも打球が伸びてこない。慌てて前進したが、グラブの土手付近にあたった打球は、無情にもグラウンドに落ちる。
「グラブに当たった位置が悪すぎて、その瞬間に『まずい、捕れない』と思いました。そこから急いでボールを拾って、バックホームをしましたが、正直よく覚えていません。落とした瞬間から頭が真っ白。スコアボードの『6-5』のスコアを見て、『とんでもないことをやってしまった』と状況を理解しました」
試合序盤から吹いていた強風のことは、もちろん、本田の頭にも入っていた。
「初回に相手の3番・佐藤くん(貴規、元東京ヤクルト)が放った打球が『追いつけるかな』と思ったところから風で左中間よりに流されて『相当強い風が吹いているな』とわかってはいたんですが……」
普段なら何事もなくさばいていたはずのフライ。「今までの野球人生で、トンネルはあっても、フライを落としたことはなかった」と振り返るように、守備に対する自信も判断を鈍らせた。
しかし、これで試合は終わらない。その裏、開星の攻撃にも大きな見せ場が待っていた。2つの死球で二死一、二塁のチャンスを作り、打席には、チーム1の好打者・糸原。カウント3-2から振り抜いた打球が、左中間を襲う。ベンチから打球を見ていた本田は、逆転を確信する。
「打球方向、角度を見て、『これは抜けるだろう』と思いました。レフトが捕球できたとしても、ショートバウンドで押さえるのが精いっぱいのはず。チーム1の俊足が一塁ランナーの代走で出ていたので、十分ホームに還ってこられると」
仙台育英は守備位置の変更を行なっており、ファーストの三瓶将大(さんぺい・まさひろ)がレフトに回っていた。1番を打つ俊足の三瓶が猛スピードで打球を追い、最後はダイビングキャッチ。風に流された打球が、グラブに吸い込まれるかのような”スーパープレー”だった。
「一塁ベンチからは、捕球されたかどうかが、はっきりとは見えなくて。『どっちだ!?』と思っていたら、審判がアウトコールをする姿が見えました。その瞬間に『終わってしまった……』と今まで味わったことのない切ない気持ちになりました」
試合後は、報道陣からプレーについて数多く質問されたが、「何かしら回答したとは思うんですが、放心状態でほとんど記憶がないんです」と振り返る。
高校最後の夏は、苦いものとなったが、進学した大阪体育大でも野球を続けた。大学で野球を続けることに迷いはなかったという。
「ここで野球から逃げてしまったら、恥ずかしいし、絶対に悔いが残る。高校時代の無念を晴らす意味でも、絶対に続けようと思っていて。迷いはなかったです」
甲子園後は大学が開催する練習会に参加。そこでも当然のように”落球”が付いて回った。
「高校の公式戦用のユニフォームを着用して練習会に臨んだのですが、センターを守ったときに、『君って、”あの”開星のセンター?』と言われることもありました。入学後も打撃練習でフライが飛んでくると『お、捕れるんかー?』とイジられることも多かったですね(苦笑)」
しかし、それは嫌がらせの類いではなく、「むしろありがたかった」と振り返る。
「気を遣って『触れないでおこう』と距離を置かれるよりは、自分としてもありがたかったですね。臆せず関わっていく、懐に飛び込んでいくのが”関西流”なのかなあ……と(笑)。反対に、高校のときのチームメイトや、クラスの同級生は、僕に配慮して触れないでいてくれて。それも優しさですし、本当に周りの人々に救われた、助けてもらったと思います」
あの落球から学んだことは何だったのか。この問いに対して現状を交えながら、本田は言う。
「どうしても『気の緩み』が出てしまうのが、人間というもの。その緩みをなくすにはどうしたらいいのか。特に自分は、『集中力を保つ』ことが大きな課題というか、一生のテーマだとも思っています。
仕事に置き換えると、ミスを繰り返さない、上司から同じことを注意されないように気を配る。日々の活動でも、お客さまと約束に遅れないように、『だろう』『だったはず』で済ませず予定の確認を怠らないこと。『気の緩みの怖さ』は、あのエラーがあったからこそ、気づけたと思います」
こう話したあと、少し名残り惜しそうな表情で、こう付け加えた。
「今でも『最後の打球をちゃんと捕球していたら、(チームは)どこまでいけたのかな』とは思ってしまいますね。仙台育英がベスト16まで勝ち進んで、興南(沖縄)に負けた。もし自分たちが勝ち進んで、興南と対戦したらどんな試合になったのか。優勝校相手にどこまで食らいつけたのか。全国で戦う力は十分あるチームだったと思うので、そこを見たかったなあ、と思います」
初めて出場したときには”天国”を、最後の夏には”地獄”を見せられた場所。その両面を味わった本田が思う”甲子園”とは。
「必ずしも”いいことばかり”の場所ではないかな……と思います。試合は1回戦から全国中継されていて、ワンプレーに対して賞賛だけでなく、バッシングも想像以上に多くある。出るからには強い決意、相応の”覚悟”を持って臨まなければならない場所だと思います」
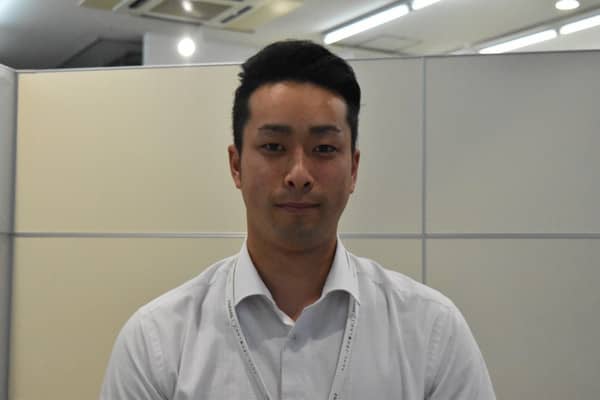
大学卒業後、地元・島根に戻り、自動車販売店で働く本田紘章氏
100回目の夏の甲子園をかけ、各地方で熱戦が繰り広げられている。今夏も全力プレーのなかで、思わぬミスが生まれることもあるだろう。そのプレーに対してさまざまな意見が飛び交い、議論が交わされることと思う。
しかし彼らには、この先も続く長い人生が待っている。大切なのは、成功や失敗から何を学び、今後につなげていけるかどうかではないか――。
あの落球から「一生のテーマ」と語る自身の課題を自覚し、覚悟を持って仕事に邁進(まいしん)する「開星のセンター」、本田紘章の姿を見て、そう思わずにはいられなかった。
大学時代のアルバイトで車に触れる機会が多くあり、そこから自動車業界に興味を持った本田は、卒業後に地元・島根の自動車販売店に就職し、今年で3年目を迎える。









































































