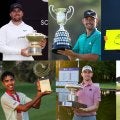齋藤学インタビュー@前編 ひとつの区切りとでも言えばいいだろうか。ようやく自分の気持ちに決着をつけたのであろう。齋藤…
齋藤学インタビュー@前編
ひとつの区切りとでも言えばいいだろうか。ようやく自分の気持ちに決着をつけたのであろう。齋藤学は、こう切り出した。
「ロシアワールドカップのメンバーが発表された後なので、今なら話すことができますね」

横浜F・マリノスを離れた齋藤学に現在の心境を聞いてみた
思わず顔を上げて齋藤を直視する。その表情は、どこか清々しく見えた。
ただ、そのひとことですべてが理解できた。齋藤がケガからの復帰を目指してもがいてきたことも、育ったクラブに別れを告げて川崎フロンターレへと移籍したことも、すべてはあの日からつながっていたのだ。
失意の2014年ブラジルワールドカップ――。
「4年前のワールドカップでは日本代表に選ばれましたけど、ピッチに立てず、すごく悔しかった。だから、それからは、自分自身に何か変化を起こさなければいけないと思って、食事の方法を変えてみたり、トレーニングの方法も変えてみたりと、いろいろなことにトライしてきた。
それこそ昨シーズン、横浜F・マリノスでキャプテンをやりましたけど、それも最初は悩んだんです。でも、キャプテンをやることで、自分自身も何か得られることがあるんじゃないかと思って引き受けたんですよね。変われるのであれば、何でもやろう、やってやろうって思っていた。
それだけ、この4年間で、ワールドカップというものは自分の中で、ものすごく大きなものになっていたんです」
結果的に、ロシアワールドカップへの出場は叶わなかった。ただ、そんな夢であり、目標をもっと早くに失いかけるアクシデントが齋藤を襲った。昨年9月23日である。当時、横浜F・マリノスに所属していた齋藤は、J1第23節のヴァンフォーレ甲府戦の試合中に負傷した。
「ケガした瞬間は、右ひざのどの部分を負傷したのかわからなかったんですよね。試合翌日にMRIを撮影して、ドクターから『全治8ヵ月です』と言われて初めてわかったんです。それで手術の予定日から逆算すると、復帰できるのは6月末。その瞬間、ワールドカップのためにずっとがんばってきたのに、もう無理だな、これで少しの望みもなくなってしまったなって思いましたよね」
右ひざ十字じん帯損傷――全治8ヵ月の診断だった。4年前、ブラジルの地で一度もピッチに立つことなくワールドカップが終わってから、次を見据えてすべてを注いできた。ケガをしたからといって、簡単にあきらめてしまうには、費やしてきた時間はあまりにも長すぎた。
「過去の事例を調べてみたら、5ヵ月で復帰している選手がいたんですよね。それで、5ヵ月で復帰できたら(ワールドカップに)間に合うかもしれないなって思って。だから自分の中で、その可能性を信じて、まずは手術するために足の腫(は)れを取ることと、足の曲げ伸ばしをなるべく最大限に保つための筋トレをすぐに始めました。
最初は誰に言っても、『あくまで目標ね』って言われました(苦笑)。自分としても、5ヵ月での復帰を目指すけど、先を見ることはやめようって決めて、まずは1日1日、やれることを100%以上の力でやろうと思った。その日のノルマがこれだけだったとしたら、それを少しだけ超える。それを毎日続けていけば、もしかしたら8ヵ月が7ヵ月になるかもしれないし、6ヵ月になるかもしれない」
そう言って齋藤は、広げた親指と人差し指を徐々にくっつけていく。指では簡単に期間を縮められるが、実際はそうたやすいことではない。
自暴自棄になってもおかしくはない状況で、なぜ齋藤は自分を奮い立たせることができたのか――。そう聞けば、「自分よりも友だちやチームメイトのほうが心配してくれて、落ちこんでいる余裕なんてなかったんですよ」と言って笑った。ひとつ言えるのは、自分自身を変えようと取り組んできた日々が、間違いなく彼を成長させていたということだ。齋藤が言葉を続ける。
「でも、あきらめるのって簡単じゃないですか。(ワールドカップのメンバーに)選ばれる、選ばれないは別として、チャレンジする過程というものが何より大事だと思ったんですよね。ここで簡単に投げ出してしまうよりも、チャレンジし続けたほうが、サッカー人生においても、その後の自分にとっても可能性は広がると思えたんです」

十字じん帯を損傷した左ひざを指しながら苦悩の日々を振り返る齋藤
それでも日々のリハビリは、前進というにはほど遠い地味な作業の繰り返しだった。何が一番つらかったかと聞けば、「ひざの周りの筋肉に電流を流して、その箇所に力を入れて負荷をかけるトレーニング」だと、自分のひざをさすりながらふたたび笑う。
走るでも、ボールを蹴るでもないトレーニング。牛歩に近い毎日の連続に、前向きになることもあれば、心が折れそうになったこともある。そんなとき、自分の支えになっていたのが、自分自身で書き記した言葉の数々だった。
「ケガをした日からもう1回、ちゃんと書き直そうと思って、新しいノートに日記というか、いわゆるサッカーノートを書き始めたんですよね」
そこにはトレーニングの内容から、つらかったことやうれしかったことまで、すべてが綴(つづ)られている。だからこそ、その当時の正確な日付も、率直な心境も、今のことのように思い出せる。
「初めて走れたときは、泣きそうになりましたよね。あれは(昨年の)12月1日でした。前十字じん帯を損傷した場合、だいたいジョギングができるまでに2ヵ月はかかるみたいなんですけど、自分の場合は1ヵ月半だったんですよ。走ったときは『うわぁ、俺、走ってるよ』って思って、走るだけで、こんなにも感動できるんだって感じましたよね。
ボールを蹴れたときもそう。右足でボールを蹴ったのは12月31日。そこはちょっとだけワガママを言って、年内のうちにボールを蹴りたいって言って蹴らせてもらったんです。それでオフに入ったんですよね」
復帰に向けてリハビリが進んでいくなか、並行して大きな転機があった。それは転機と表現するには軽く、日本サッカー界に激震が走ったとでも言えばいいだろうか。8歳から横浜F・マリノスの育成組織で育ってきた齋藤が、川崎フロンターレへの移籍を決断したのである。
その過程での葛藤や苦しみ、そして心境の変化に至るまで、サッカーノートにはしっかりと記されているという。
「リハビリに励んでいる最中に、クラブからショックなことを言われて悩みましたし、自問自答もしました。僕は8歳から横浜F・マリノスで育ちましたけど、同時にもうひとつ、自分の中にあるのは、僕は川崎市に住み、川崎市の小学校に通っていて、川崎フロンターレというクラブが自分の住んでいる町にどれだけ根づいているかを肌で感じてきたということ。ホームスタジアムのある等々力陸上競技場に近い町に住み、フロンターレの存在を身近に感じてきた。
だから、自分にとってはフロンターレでプレーするのか、それともマリノスに残るのか、そのどちらかしか選択肢はなかったんです。本当に悩んだ時期は苦しかったですけど、最終的には、自分が外に出て、自分自身がどう変わっていくのかを自分でも見てみたかったんです」
物心(ものごころ)がついたころから、横浜F・マリノスで育ってきた。サッカー人生のほとんどを、そこで過ごしてきたと言っていい。川崎フロンターレでプレーする今、地元への愛着を語るように、育ってきたクラブへの思いが簡単に消えることはない。
「何を言っても誤解される可能性もあるし、わかってもらえない可能性もある。それに、そこを去る人間がいろいろと言って出ていけば、残された人たちがつらくなる。僕はそれがわかっているから、何も話さなかったし、言わないことにしたんです」
それだけで十分だった。いつか本人の口から、すべてが語られるときが来るのかもしれない。だが、彼は口をつぐむことで、すべてを背負うことに決めたのである。
すべてを話すことが、思いの丈(たけ)を語ることが、真摯であり、愛情とは限らない。それは誰よりも、齋藤自身が身をもってわかっていたのである。
(後編に続く)
>
>