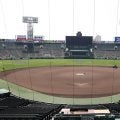完全復活への鮮やかにして克明な足跡を刻んだのは、6年ぶりに出場したモンテカルロ・マスターズの「赤土の上」だった。モ…
完全復活への鮮やかにして克明な足跡を刻んだのは、6年ぶりに出場したモンテカルロ・マスターズの「赤土の上」だった。

モンテカルロ・マスターズで準優勝して完全復活を印象づけた錦織圭
右手首のケガによる戦線離脱から、約半年ぶりに復帰したのが今年1月下旬。始まりは、ランキング200位台の選手に競り負ける失意の敗戦である。その苦境から這い上がり、ツアー大会でトップ選手との対戦を重ね、勝利からは自信を、敗戦からは課題を汲み上げながら、ついに彼はATPマスターズ1000の決勝の舞台へと舞い戻った。
しかも、そこに至るまでに倒した選手のリストには、18位のトマーシュ・ベルディヒ(チェコ)を皮切りに、3位のマリン・チリッチ(クロアチア)、そして4位のアレクサンダー・ズベレフ(ドイツ)ら新旧スターの名が並ぶ。
戦いの内容に目を向けても、掴みかけた勝利を目前で取り落としながら最終的に3時間の死闘を制したチリッチ戦、そして試合のなかで攻略法を再構築して逆転勝ちした準決勝のズベレフ戦など、勝利への執念とテニスへの情熱がほとばしる激闘揃い。3週間前のマイアミ・マスターズでの敗戦後に残した「もうちょっとのところにいるのかな、というのは感じます」との言葉が正しいことを、彼は自らのラケットで証明した。
キャリアのなかで度々ケガの試練に面してきた錦織圭だが、選手生命を脅かしかねないそれからの帰還となると、今回が2度目と言えるだろう。
1度目は、19歳のときに経験した、ひじの手術。原因不明の痛みに悩まされた期間も含め、11ヵ月の長きにわたり公式戦から遠ざかった。手術直後は動かぬ右手にショックを受け、先の見えぬリハビリの日々から逃げ出したこともある。
「以前にいた場所に戻れるのだろうか……」
それは当事者のみならず、彼を支える家族やスタッフたち全員が抱えた恐怖だった。
ケガの功名――。そんな言葉を周囲の人々は口にしたが、プロとしてのキャリアも浅かった19歳は「この経験をプラスにしろと言われたって、離脱しているのにプラスに考えられるわけないじゃないか」と心のなかで独りごちた。それでも現状を克服し、未来につなげるためには、何かを変えなくてはならないことはわかっている。「ひじに負担のかからない打ち方に変えるべき」との助言も、複数の関係者から受け取った。
このとき、錦織の周囲の人々の間では「打ち方を変えたら違うプレーヤーになってしまう」と反対の声も上がったという。だが、錦織の父親は「違うプレーヤーになったって構わない。大切なのは、ケガの再発を防ぐこと」と、フォームの改善を後押しした。
「あいつには、30歳になっても飛んでいてほしいけん……」
復帰したばかりの息子を見て、父親はポツリと、そうこぼした。
今回、手首のケガでテニスを長く離れたとき、錦織は今の自分を、8年前の自らと時折重ねることがあったという。
「あのときは、なんか無理やり自分のなかでプラスにしなくてはいけないという焦りもあった。今回はいろいろと経験して、自分がこれからもケガと付き合っていかなくてはいけない身体だと十分に認識しているので、だいぶ落ち着いて……無理やりプラスに考えようとしなくても、けっこうポジティブにいられます」
復帰のめどがおぼろげながら見え始めた昨年末、錦織は心の現在地をそう述べた。痛めた手首への負担を軽減するために、サーブフォームの改善にも自ら積極的に取り組む。以前はトスの後に右足を軸足へと引き寄せていたが、「安定感を上げるため」に、肩幅ほどに開いたまま打つようにもした。
「サーブは徐々によくなっていますね。手首に負担がかからないようにしたいので、その意味ではよくなっています。足を動かさないフォームも、あれに変えてから打ちやすくなった。慣れが必要なのでもうちょっと長い目で見ないといけませんが、サーブはよくしていきたいです」
これは先月のマイアミ・マスターズ時に、錦織が口にしたフォームへの手応えである。今回のモンテカルロではまだ好不調時の差が大きかったものの、準決勝のズベレフ戦では、要所でのサーブの安定感が窮状を切り抜けるカギとなった。
19歳のときには素直に受け入れがたかった「ケガの功名」が存在することも、今の彼は知っている。特に8年前に実感したのが、右手が使えない間に左手でボールを繰り返し打った成果としての、バックハンドの進化だった。多くの選手を畏怖(いふ)させ、今回のモンテカルロでも幾度もウイナーを奪ったバックハンドの逆クロスやストレートへの強打は、ケガを克服したからこそ手にした武器だ。
今大会の錦織は、飛び上がりながらバックを放つ”ジャックナイフ”を幾度も披露した。ズベレフ戦ではジャックナイフをフェイントにドロップショットを沈める妙技で、観客の歓声とため息を誘いもした。
父親が「飛んでいてほしい」と願った30歳を2年後に控えた今、彼は赤土を蹴り上げながら、ふたたび大きく飛翔しようとしている。「苦しみながらも、楽しんでできると思う」と言っていたように、頂点へと駆け上がる道中の景色を楽しみながら――。
>
>












![19歳・坂本怜が快勝で予選決勝進出!シード撃破で初めてのグランドスラム本戦へあと1勝[全豪オープン予選]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/)