上田二朗が模倣した南海のレジェンド・杉浦忠「私の心の支え」 徹底的に真似した。1973年に阪神で22勝を挙げた上田二朗氏…
上田二朗が模倣した南海のレジェンド・杉浦忠「私の心の支え」
徹底的に真似した。1973年に阪神で22勝を挙げた上田二朗氏(野球評論家)は1966年の東海大進学後、メキメキと力をつけていった。和歌山・南部高2年夏(1964年)から取り組んだ下手投げも大学で進化したが、これには東海大・岩田敏監督からの指令が大きく関係していた。1959年に38勝4敗の成績を残すなど、“史上最強のアンダースロー”と呼ばれた南海・杉浦忠投手の投球フォーム写真を部屋中に貼れというものだった。
1966年、東海大1年の上田氏はいきなり首都大学春季リーグ開幕戦先発を任され、完投勝利を挙げた。入寮した時に岩田監督から開幕投手に指名されており、期待に応える快投だった。「その春のシーズンは4勝したと思う。秋も投げさせてもらって1年間でも結果が出ましたね」。1965年の高3夏、和歌山大会準々決勝で市和歌山商戦に完投勝利を飾って注目を集めたものの、2番手投手。そんな右腕が大学入学と同時に素質を開花させた。
飛躍を呼んだ要因の1つが、杉浦の写真だ。実は岩田監督に開幕投手を命じられた時に併せて、こんな指令も出されていた。「お前は知っているかどうか知らんけど、東京6大学(立大)に杉浦忠というものすごいピッチャーがおったやろ。今、南海ホークスで活躍しているけどな。杉浦の投げ方にお前はよく似ている。新聞社から杉浦の分解写真を何枚でも取り寄せてやるから、天井や壁に全部貼れ。寝ても覚めても杉浦の写真を見ろ!」。
上田氏は懐かしそうにこう話す。「岩田監督は明大出身で、杉浦さんとはよく話をしていたそうです。もちろん、私も杉浦さんのことは知っていましたけど、この話の後、同級生のマネジャーが本当に写真を貼りに来たんですよ。1年の時は2人部屋だったんで、もう1人の選手に悪かったんですけど、どっち向いてもこっちも向いても杉浦さんの写真でした。2年からは1人部屋にならせてくれたんですけどね」。
実際に真似したそうだ。「杉浦さんが足を上げてリリースするところまでの全部の分解写真をくれましたからね。監督も『俺は杉浦のフォームを知っているからそれをやれ』ってことでしたしね。杉浦さんと同じようにやったつもりです」。それが大きなプラスになった。「私の心の支えでしたよ。それがなければ、アンダースローで何をどうしていいか、その時でもほとんどわかっていませんでしたからね」。
杉浦氏本人に「ずっと真似させてもらって結果が出るようになりました」
上田氏は1964年の南部高2年夏過ぎ、山崎繁雄監督に「アンダースローに変えろ」と言われて下手投げに転向。それが大学時代に開花した形だ。「山崎監督には変えろと言われただけで、カーブの投げ方とかシンカーの放り方とかは握りを教えてもらって『あとは自分で工夫せぇ』ってことだった」という。当時はフォームを変えたばかり。最初からいろいろ詰め込まないように、ということでもあったのだろう。
それが大学で一気にバージョンアップした。「岩田監督は『普通のアンダースローはこうやって潜るけど、杉浦の場合は立っていって潜る時、投げる時には前で最後の最後にボールを離すんだ』とかいろいろ教えてもらいました。普通のアンダースローは秋山(登)さん(大洋)のようなシュンと切る回転式投法。杉浦さんの場合は下半身を使っての押し込み型投法。それによってボールの重さも回転も違うということも聞きました」。こうしたことを理解した上で杉浦投法を模倣した。
「好む好まないに関わらず、目が覚めたら杉浦さんの写真が目に入りますからね。あと岩田監督に言われたのは、肘から指先までを意識して寝転んで天井に向けてボールを投げて、同じところに(ボールが)返ってくる練習を寝る前に必ずしなさい。暇さえあれば電車の中でもどこでもいいからボールを持って指先のマメを作りなさい。指先の力を強くしてボールを離す時にはパチンパチンと言わせなさいとかね。本当に監督は私の指導に力を入れてくれました」
すべて“杉浦投法”に通じるものでもあった。上田氏は1969年ドラフト1位で阪神に入団したが、「オープン戦で(南海の)杉浦さんに話を聞きに行ったことがありました」と明かす。「(阪神の投手兼任監督だった)村山(実)さんに『俺が話をしといてやるから行ってこい』と言われてね。いろいろ質問もしたし『大学1年からずっと真似させてもらって結果が出るようになりました』という話もしました」。大学時代に日々接した杉浦氏の写真。効果はまさに絶大だった。(山口真司 / Shinji Yamaguchi)







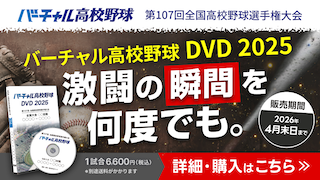








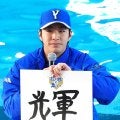
























































![アルカラス、難敵ポールを退け3年連続の8強進出!史上最年少の生涯グランドスラムに邁進[全豪オープン]](https://img.sportsbull.jp/thumbnail2/2026012516260245513700.jpg)



