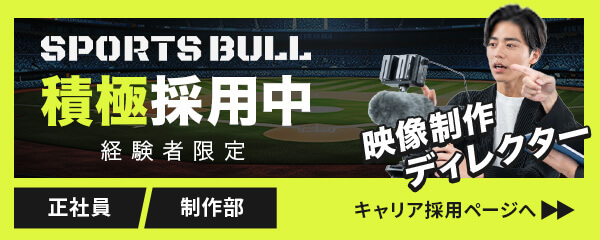『氷上のフェニックス』(小宮良之:著/KADOKAWA)の続編、連載第6話 岡山で生まれた星野翔平が、幼馴染の福山凌太と切磋琢磨しながら、さまざまな人と出会い、フィギュアスケートを通して成長する物語。恩師である波多野ゆかりとの出会いと別れ、…
『氷上のフェニックス』(小宮良之:著/KADOKAWA)の続編、連載第6話
岡山で生まれた星野翔平が、幼馴染の福山凌太と切磋琢磨しながら、さまざまな人と出会い、フィギュアスケートを通して成長する物語。恩師である波多野ゆかりとの出会いと別れ、そして膝のケガで追い込まれながら、悲しみもつらさも乗り越えてリンクに立った先にあるものとは――。
今回の小説連載では、主人公である星野がすでに現役引退後の日々を送っている。膝のケガでリンクを去る決意をしたわけだが、実はくすぶる思いを抱えていた。幼馴染の凌太や橋本結菜と再会する中、心に湧きあがってきた思い...。
「氷の導きがあらんことを」
再び動き出す、ひとりのフィギュアスケーターの軌跡を辿る。
登場人物一覧>> 第1話>>無料 第2話>>無料 第3話>>※有料 第4話>>※有料 第5話>>※無料

第6話 メンタルトレーニング
夏の匂いが濃厚に感じられるようになっていた。フィギュアスケートのシーズン前哨戦が、各地で活発に行われる季節だ。
星野翔平は神戸で行われる大会を、再デビュー戦に設定していた。
その仕上げに、都内で心理カウンセリングを受けることになった。リンクに立ったフィギュアスケーターは、たった一人ですべての注目を浴びる。その心理的ストレスは尋常ではない。他のスポーツでもメンタル面の取り組みが叫ばれている中、もっと脚光を浴びてもよかった。
「復帰、おめでとう。また新しいことをやってのけるんだね」
メンタルトレーナーの夏八木廣は、そう言って翔平を歓迎してくれた。
「現役引退以来、ご無沙汰しています」
初めて出場したモスクワ五輪後からの付き合いで、膝のケガで苦しんでいた時も心強いカウンセリングを受け、とても頼りにしていた。現役復帰を電話で伝えた時、重低音の温かみのある声に励まされる思いだった。
夏八木は名優モーガン・フリーマンを思わせる、佇まいだけで雰囲気を醸し出すようなところがあった。何気ない仕草に味がある。低い声に渋みが混ざったリズムは、不思議なほど気持ちを落ち着かせた。
カウンセリングの部屋は1年前にリフォームしたらしく、白い壁に囲まれた部屋に薄いグレーの三人がけソファと紺色の一人用ソファ、真ん中には木製のテーブルが置かれ、足元には薄いグレーのフロアマットが敷かれていた。パキラのプランターが一つ、隅っこには間接照明が灯され、ウッドブラインドの隙間から木漏れ日が入って、温かみを感じさせる空間だった。
「私の仕事は変わらない。君の話を聞くことだ」
「はい」
「でも、長い付き合いだから言わせてもらう。期待と不安の両方で少しパンクしかけているね」
夏八木は心中を見透かすように言った。あまりにそのとおりで、少し驚いた。カウンセリングに来ているくらいだから、メンタル強化目的はわかり切っていたが、両極端の気持ちに押し潰されそうだった。
「先生はお見通しですね」
「人間の気持ちは、そんな簡単な構造じゃないから。強い決心をした場合、それだけの負荷もかかる。巨大なプラスとマイナスが両方発生するんだよ。だから、何も新しいことに挑戦しない人の方が心理的なダメージも少ない。ただ、それは潜在的にそうした強い不可に耐えられないことを予感しているから、踏み切れないんだよ。心は輪廻のように行動とつながっているんだ」
夏八木の言葉は、現役復帰を決心した翔平の気持ちにすっと入ってきた。短く切りそろえた髪やひげには白いものが多くなったが、声の艶はむしろ増したようだった。
「『心は鋼鉄ではない、または鋼鉄であってはならない』って夏八木さんはいつもおっしゃっていますもんね」
「そう、柔らかくて、ぐにゃりと曲がる。ゴムみたいなのが理想だよ。だからこそ元に戻るし、ぐっと伸びて縮んでパワーも生み出す。鋼鉄の棒は強そうだが、ぽきりと折れたら元に戻すのは難しい。翔平君が不安に感じるのは、むしろ健全なんだよ。それだけ心に負荷がかかっているし、そうでなかったら、現役復帰なんて成し遂げられないんだろう」
夏八木は優しい声音で言った。
「やっぱり、不安は拭えないんですよね」
「それは、君が頑張っているという証拠だよ。間違っていない。これから、もっと不安は大きくなる。迷いが出て、パフォーマンスが下がって、そのことに落ち込む。積み上げてきたものがすべて崩されるような怖さに襲われるかもしれない。しかし、その不安は決心と努力の裏返し。たとえ失敗しても、君が生きてきた事実は決して変わらない。生きる姿勢こそを問うべきなんだ」
その言葉に、翔平は小さな感動を覚えた。
「生きる姿勢を問う......」
「失敗してもいいんだよ。所詮、人は常に何かを得て、何かを失う。その中で生きる答えを見つけていけばいい。これが正解、なんてないんだよ。そもそもヒーローっていうのは、もともと簡単ではないことに取り組む性分があってね。人が『そんなことしなくてもいいじゃん』『何の意味があるんだよ』っていうことをする。それが、翔平君には生きる意味なのさ」
「生きる意味」
「今の時代、世界は混乱の極みにある。独裁者が勝手に他国に押し入って、我が物顔で殺戮を繰り返す。報復行為を拡大解釈し、町を徹底的に破壊、市民を餓死まで追い込む、どちらがテロリストかわからない戦闘もある。大規模な気候変動を引き起こし、洪水であらゆるものを流されてしまう町、地獄の炎のような大火事に見舞われる町もある。あるいは平和に見えても、政治家の汚職が横行し、それをコントロールできる人もいない。炙り出された世界の構造に、誰もが辟易している。でもね、翔平君はそこに生きる意味を与えられるんだよ」
「そんな大それたことはできないと思いますが......」
「すでにやっているよ。君の高潔で挑戦的な生き方が、それを見た人の道標になっている。世界、と言ってもね、結局は一人の気持ちからしか変わらないんだよ」
「フィギュアスケートを裏切らないように、とは生きてきました」
「そこまでスケートに真っ直ぐでいられるのは、神様からのギフトさ。きっと、君は何かを失っているんだろうけど、それ以上の何かを得ている。これは、アーティストと呼ばれる人たちの条件だ」
過去の芸術家たちも、何かを失うことで圧倒的な何かを得てきたという。
たとえばドイツ人音楽家のルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、20代後半に聴覚の障害を抱え、30代でほとんど音を失った。絶望感に苛まれ、自死も考えたという。音楽家にとって音がない世界は無に等しかったが、彼はその喪失感の中で、傑作を残した。40代で完全に音を失う中、書き上げたのが、世界的に有名な『交響曲第9番』だ。
また、スペイン人画家のフランシスコ・デ・ゴヤは若い頃は、王立アカデミーに出品したが、二度も落選した。その後はタペストリーの下絵描きから宮廷画家に出世したが、30代までは歴史に名を残すほどの人物ではなかった。
しかし40歳になって重い病気にかかり、聴力を失って以後、絵の重厚感が変化した。『カルロス4世の家族』、『着衣のマハ』、『裸のマハ』、『マドリード、1808年5月3日』、『巨人』など次々に名作を描き上げた。また、当時はナポレオン将軍が率いるフランス軍がスペインに侵攻し、戦乱の最中だったが、その筆はむしろ冴え渡った。
そして晩年のゴヤは、「聾者の家」と呼ばれた別荘で14枚の壁画群『黒い絵』を飾って過ごした。黒い絵は『我が子を食らうサトゥルヌス』に代表されるように、不気味な絶望がたゆたう。しかし、一人の人間として目が離せなくなる魔力のようなものを持っていた。
喪失によって、痛みを知ることで、ベートーヴェンも、ゴヤも何かを得たのだ。
「一度、翔平君がアイスショーに招待してくれたことがあったね。正直、驚いたよ」
夏八木は、さわやかな風を吹かせるように言う。なぜ、彼の言葉一つひとつに力があるのか、わからない。
「お忙しいのに、おいでいただきありがとうございました」
「礼を言うのは私の方だよ。フィギュアスケートは、こんなに感情に訴えるものなんだなって思った。楽曲に合わせて、人生の喜びや悲しみが表現される。それはね、言葉では説明しにくい、胸が揺さぶられるものがあった。私は心理構造を論理的に考えるのが仕事だが、私の心に飛び込んできた感覚は、説明しがたい非論理的なものだった。たぶん、それは共感のようなものだろう。翔平君が膝のケガの苦しみを抱えながら、そのつらさを一切出さず、亡くなった恩師を忘れずに感謝し、優雅に華麗に舞い踊る。その姿を私は応援しながら、自分の人生までが応援された気持ちになった。もちろん、それは自分の解釈で、それぞれの思いに訴えているから、解釈は自由で解き放たれているんだろうけど」
「それがフィギュアの芸術性ですね」
「大勢のファンは、君の滑りで『何かに縛られないでいい』と囁いてもらえるんだろう。それは非日常とも言えるけど、究極の日常とも言える。まあ、それも私の解釈に過ぎないんだがね」
多くの偉人たちは少なからず何かを欠いていたことで、圧倒する力を与えられているという。
レオナルド・ダ・ヴィンチ、アルベルト・アインシュタイン、トーマス・エジソン、モーツァルトなどの偉人たちはいずれも、アスペルガー症候群の兆候があったとされている。何か一つの物事に対し関心を示すと、他のものを忘れるほどに夢中になって極めていく。ある有名なアスリートが冷凍保存して小分けにしたカレーを毎朝、温めて食べていた逸話も近い傾向なのかもしれない。一つのことに固執することで何かを失い、同時に得ているのだ。
何かを極める人間は、自ずと何かを犠牲にしていると言われる。彼らが健全な生活を保つには、「何かを失いながら何かを極めていく方が理にかなっている」という学説もある。
「翔平君は"最後の日"が来るまで滑り続けるんだろう。それが最大の幸せなんだから、宿命や運命と呼ぶべきかな。苦しさも含めて、君は挑んでいくことになるが、その瞬間こそが幸せなのかもしれない。その姿が喝采を浴び、リンクの中で幸せを共有する。点数や順位はあまり関係ない。それを超越したものに対し、思いの渦が作られる」
夏八木はそう言って立ち上がると、ブラインドを少し閉じた。日が暮れていたようで、間接照明が入れ替わるように淡い光を放った。
「気分が楽になりました」
翔平は言った。
「物事はちょっとしたことで、大きく変わる。翔平君は、それを人生の中で知っている。そんな君を支えてきた人たちが大勢いる。困ったときは、そういう人たちに問いかけるといい。もちろん、私のことも頼ってほしい。そのために、自分は存在しているんだから」
夏八木は立ったまま、ソファの背に手をかけながら言った。
翔平は、その姿に頭を下げた。再デビューに向け、気持ちが整った。