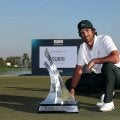「対話重視」の石川亮が重宝される理由 ベンチ最前列で大きな声を上げる“新戦力”の存在が際立つ。昨オフに日本ハムからオリッ…
「対話重視」の石川亮が重宝される理由
ベンチ最前列で大きな声を上げる“新戦力”の存在が際立つ。昨オフに日本ハムからオリックスへトレード移籍した石川亮捕手が、和やかな雰囲気を構築している。爽やかなルックスにも注目が集まる27歳は「とにかく、気負ったらダメ。僕にカッコつける理由なんてサラサラないので。良い意味でふざけ倒していきたい」と、新天地でもナインを鼓舞している。
石川は、同学年の森友哉捕手、若月健矢捕手、さらに1学年下の頓宮裕真捕手らと激しいポジション争いを繰り広げる。7日終了時点で開幕から55試合が経過し、石川の出場は6試合。スタメンマスクは1試合で、打席に入った回数も計4度だが“必要不可欠”な戦力として、輝いている。
捕手として心掛けているのは「対話」で、仲間との積極的なコミュニケーションを欠かさない。「相手を知りたければ、自分をさらけ出すこと。その後は、相手が決めることなので。100人いれば100通りの好みがありますからね。だから、僕は100を知る努力をしたい」。宗佑磨内野手から「あの人はヤバい(笑)。面白いし、馴染む力がありすぎる」と絶賛され、天然キャラの紅林弘太郎内野手でさえ「亮さんは距離感が近すぎる」と表現する“コミュ力おばけ”が、仲間を笑顔にするシーンは目立つ。
18歳で入ったプロ野球の世界で多くの衝撃を受けてきた。石川は2013年ドラフト8位で帝京高から日本ハムに入団した。1学年上のエンゼルス・大谷翔平投手とは日本ハム在籍時、4年間を共にプレー。バッテリーを組み、数々の学びがあった。
「翔平さんは、肝が据わっている。度胸満点。試合前に不安要素のある言葉は一切、出てこないんです。試合が始まる前から野球を楽しんでいて『早く投げたい』と、ずっと言っていた。僕も近くで見ていたので、すごく勉強させてもらいました」
「意見交換して、改めて自分の考え方を伝えることで、ようやく相手に理解してもらえる」
投打二刀流の“スーパースター”から得たのは技術力向上だけではなかった。「僕はプロに入ったとき、めちゃくちゃ意識していたことがあります。先輩の話を聞くことに没頭していました。まずは、その人(の考え方)を知らないと始まらない。そこで共感できるか、少し違うなと感じる。その瞬間に、ようやく自分(の考え方)を知ることができる。意見交換して、改めて自分の考え方を伝えることで、ようやく相手に理解してもらえるんです」。真っすぐな目で話を続ける。
「よく言うじゃないですか。広く浅くか、狭く深くか、なのか。僕は『広く深く』を心掛けています。本当にいろんなことが知りたい。どんどん吸収させてもらって、成長していきたい。僕が思っていた以上に、オリックスの選手たちは人が良すぎて、この感じ(雰囲気)で馴染ませてもらっています」
試合前にはスタメン出場する選手の緊張を解き、得点した際には一緒に喜びを分かち合う。「僕一人で全てを変えられるわけではないですけど、そのきっかけになれたらなと思っています。ムードを作る時は、誰かが1発目に踏み込まないと。例えば負けているとき、ずっと停滞している雰囲気で楽しいわけがない。タイミングと場面を見て、盛り上げられるような心掛けはしています」。先発投手がイニング間に行う、ベンチ前のキャッチボール相手を務めたり、本塁生還した選手をベンチ最前線で迎えて祝福したり……。背番号37は、どこにでも“出現”する。
移籍1年目のシーズン。27歳は、周囲への感謝を忘れない。「みんなが、僕の性格を理解してくれるのが早かった。『こいつ、イジって大丈夫だ』と(笑)。すごくありがたいです。良い人が多すぎて僕、どんどんチームにのめり込んでいます」。明るい性格の石川の周りには自然と選手が集まってくる。「僕は“かまちょ”なんで(笑)」。ノリノリのキャラクターも愛される理由だ。
プロ入り10年目。経験も豊富になってきた。「チームの雰囲気がボーンと落ちているときでも、向きを変える必要がある。次の日、また次の日って記憶を更新していかないと。シーズンはアップデートの連続で強くなれる。ちょっとしたメンタルの切り替えで(守備で)1歩前に出れたり、ヒットが1本出たりする。そういう精神的なサポートは誰にでもできる。野球の技術以外の面で勝敗を変えられる可能性がある。僕はそういう人間でありたい」。サラッと力強い言葉で、説得する。
甘いマスクの“2枚目”は「初めて聞いたわぁ(笑)。2枚目って、どういう意味ですか?」と照れながら言葉の意味を聞き返す。そんな“3枚目”のキャラクターもこなす。決して、誰もができることではない。(真柴健 / Ken Mashiba)