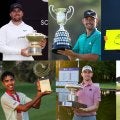元女子バレー日本代表齋藤真由美インタビュー 前編 1980年代後半から1990年代にかけて、女子バレー界の人気をけん引し…
元女子バレー日本代表
齋藤真由美インタビュー 前編
1980年代後半から1990年代にかけて、女子バレー界の人気をけん引した選手のひとりである齋藤真由美。10代のうちに全日本(日本代表)デビューを果たすなど実力もさることながら、端麗な容姿でも人気を博した。
しかし、バレーボール人生は波乱に満ち溢れていた。学生時代から続いた"戦い"の歴史を齋藤が振り返る。

現役時代、美人バレーボーラーとしても人気だった齋藤(『バレーボールマガジン』提供)
***
――バレーを始めたきっかけから教えていただけますか?
「もともとはスポーツにまったく興味ない子どもでした。小4から小6まで、原因はよくわからないんですが、いじめに遭っていたんです。6年生の時にはもう身長が168cmあって他の子より大きく、ちょっと内向的なタイプだったからかもしれませんね。今はすごくおしゃべりですが(笑)。
物事にもあまり関心がなかったんですが、4つ上の兄が心配してくれて、『みんなで目標を持って協力し合えるスポーツは楽しいよ』と勧められたのがバレーボールだったんです。それで、未経験のまま中学校でバレー部に入りました。しばらくはボール拾いや応援だけでしたが、当時の私には『毎日、自分にやれることがある』ということが新鮮でした」
――最初はプレーする機会がなかったんですね。
「でも1年生の時、大きな大会がある3カ月くらい前に、小学校からバレーをやっていた同学年の子が小指を骨折してしまって。それで周囲が『経験はないけど大きい子がいるじゃないか』となって、ルールやオーバーパスなどを教えてもらって、初めて試合に出たんです。
その試合は負けてしまったんですけど、私はすごく楽しかったですね。未経験者が入ったから負けたという雰囲気にもなったんですが、そこで指導者の方が『チームで助け合わないといけないのに、みんなで誰かの責任にするのはよくない』と言ってくれたのがうれしかった。そして何より、『自分を表現できる場所がここにあるんだ』というのを知って、どんどん練習するようになっていきました」
【「大人」への不信感】
――その後のバレー部での活躍はどうだったんでしょうか。
「3年上の先輩たちが全国大会に行ったことがあったので、『じゃあ私たちも』とモチベーションを高めました。2年生でキャプテンになり、全国大会に出場することができたんですが......結果は1回戦負け。私たちの目標は『全国に行くこと』で、その先を考えていなかったから勝てなかったんでしょうね。
でも、"目標は自分を生かす材料になる"と気づくことができ、より高い目標を実現するために、強い高校に行ってもっと自分を磨きたくなって。卒業前にいろんな高校から声をかけていただいたんですけど、都内の強豪高校に進むことを決めました」
――ただ、齋藤さんは1年生の時に中退されていますね。
「そうですね。中学校の時はわりと自由にやらせてもらっていたんですが、当時は名門校になるほどスパルタでしたから、肉体的に追い込まれるだけではなくて、すごくキツい言葉や"手"が出ることもあって。しかも、そうなるのは選手の責任という時代。『スポーツは楽しむもの。自分を出せる場所』だと思っていた私は不信感を抱くようになりました。
1年生でレギュラーになり、インターハイは3位になったのですが......そのあと、国体のメンバーに選ばれた時、自分の意思とは関係なく辞退をさせられてしまったんです。私は選ばれたことも知らず、『辞退した』という報告だけ聞きました。3年生が抜けるタイミングでしたから、『新チームを作るために、申し訳ないけれど今回はチームに残ってくれないか』といった相談があれば納得できたんでしょうけどね。
それが追い討ちになってバレーも大人も嫌になって、目標も失って。学校を中退して3、4カ月くらい引きこもっていました。当時は若さもあって『嫌なものは嫌』と頑なになってしまい、監督さんともきちんと向き合ったり話をしたりすることができませんでした」
【リハビリから復帰間近にまさかの事故】
――中退をしたあとの1986年11月には、イトーヨーカドーに入社することになります。どういった経緯があったんですか?
「中退の噂が広がり、『バレーの楽しさを知る前にやめてしまうのはもったいないから、一度うちのチームに顔を出してみたら?』と声をかけてくれたのがイトーヨーカドーなんです。当時の前田健監督、そのお父さんも、私が通っていた高校で指導した経験があったからかもしれません。それで、『やることもないし、練習を見に行くだけならいいか』と。
そこで"実業団"というものがあること、給料をもらいながらプレーできることを知りました。両親が幼い頃に離婚して、母親に育てられて決して裕福な家庭とは言えませんでしたから、『なんとか自分も支えたい』と、イトーヨーカドーに飛び込んだ形ですね」

現在は食品ブランド「株式会社MAX8」の代表を務める
photo by Matsunaga Koki
――翌年2月にはデビューを果たしますが、当時の状況はいかがでしたか?
「練習が厳しいことには変わりありませんでしたし、企業間の敵対意識も強かったですから、『すべてのチームが敵だ』という思いでやっていましたね。プレースタイルも完全に"超攻撃型"で、とにかく相手をねじ伏せることを考えていました。心のモヤモヤの部分を、すべてバレーで放出していたわけですから、大きなパワーにもなりますよね(笑)。ある意味、厳しい環境への反抗心をプレーに還元できたのはよかったのかもしれません。
でも、本来であれば高校生の年齢である私がレギュラーになると、先輩たちがスタメンから外れるわけですから風当たりが冷たくなるんですよ。性格も"心を開かないどら猫"のようになっていったというか、『誰に何を言われても、プレーで黙らせられるくらい強くならないといけない』と思っていました。ものすごく生意気な後輩だっただろうな、と自分でも思います」
――そんななか、1988年には17歳で、ソウル五輪の第1次候補選手に選ばれましたね。
「私は技術がなく、がむしゃらに打つだけの選手だったので、全日本の練習や試合も掛け持ちするうちにどんどん体を酷使して......19歳の頃には右肩が上がらず、クシで髪をとかすこともできないくらいになっていました。それで約2年間はコートに立てず、必死でリハビリを続けて、ようやく動けるようになった時に......今度は交通事故に巻き込まれてしまったんです。
トラックのドライバーの飲酒運転と居眠りが原因でした。たまたま帰省で実家に帰り、食事に出かけた帰りがけ、家族が乗っている車に正面衝突されて。運転していた兄、助手席に乗っていた私も大ケガを負い、後部座席に乗っていた母は両肩を脱臼して身体障害者となりました。
私も脱臼や額を13針縫うなどしましたが、特にひどかったのは両ひざ。手術をしたものの、『このケガをしてまたプレーができるのか。たとえコートに立てても、自分を奮い立たす力が出るのか』と、まったく先が見えませんでした」
【メンタルがやられた中での「支え」】
――そんな時に支えになったのは?
「私が入った救急病院では、70代の看護師さんに本当にお世話になりました。救急病院には鏡がなくて、自分の顔がどうなっているのかわからないんです。フロントガラスに強打して、いろんなところにガラスが刺さっていたわけですから、ひどい状態なのは覚悟していましたけどね。その時に看護師さんが、『女の子だし、顔がどうなっているか気になるよね』と、自分のカバンから小さな手鏡を出して顔を見せてくれたんです。
鏡に映った自分の変わり果てた顔に落ち込みましたが、その時に看護師さんが『あきらめちゃダメよ。頑張っていれば、その傷が人生の勲章になる時が必ずくるから』と言ってくれて。その言葉が支えになり、どんなことに対しても努力を続けてこられたと自負しています。この傷は何があっても乗り越えられる"勲章"と思うことができるようになりました」
――壮絶な経験ですね......。結局、復帰までにどれくらい時間がかかったんですか?
「手術後から約4年半なので、その前の肩のリハビリと合わせるとトータルで約6年半、コートから離れていました。全日本で活躍できていた時などは周囲に人が多く、最初のリハビリ中は応援の声も届いていましたが、時が経つにつれてなくなっていき、"ひとりぼっち"になっていく感覚がありました。イトーヨーカドーの体育館は地下がトレーニングルームになっているんですが、上でみんなが大きな声を出しながら練習しているなかでリハビリをしているうちに、メンタルをやられてしまって。
チームドクターの安井慎太郎先生の病院に転院して、母と一緒に1年くらいお世話になりました。場所は北海道でしたが、『ちょっとバレーから離れたほうがいいだろう』ということで。いろいろな治療が繰り返されて少し落ち着いた時に、安井先生が『体は動かなくても、アドバイスしたりすることはできるだろう』と、道内の少年団バレーチームの練習に連れて行ってくれたんです。
そのチームはあまり強くありませんでしたが、みんな目がキラキラしていて。当時、眉毛もすべて剃って、手術明けの宇宙人のような顔をした私に『教えて、教えて』と聞いてくるわけです。そこで自分のことを振り返ったんですよね。『負けない』『攻める』『つぶす』とか、そんなことばっかり考えていて、自分が求めていた『楽しむこと』がまったくできていなかった。その子たちに会って、『こんな目を取り戻したい』と思うようになりました」
――その後のリハビリはいかがでしたか?
「歩くこと、走ること、ボールを投げること......とにかく目の前のひとつずつを目標にして、クリアしていきました。再びコートに立たなければ、『楽しむこと』ができないままバレーをやめることになってしまうと奮起して、またチームに戻ってリハビリを始めました」
(中編:禁断の移籍を決断させた名将の言葉>>)
■齋藤真由美(さいとう・まゆみ)
1971年2月27日生まれ、東京都出身。1986年に15歳でイトーヨーカドーに入社し、エースアタッカーとして活躍。17歳で日本代表に選出された。その後はダイエー、山形県・天童市が本拠地だったパイオニアに移って活躍し、2004年に引退。引退後は解説者や天童市の教育委員などを経て、益子直美の「監督が怒ってはいけない大会」に参加。自身は「株式会社MAX8」の代表を務める。